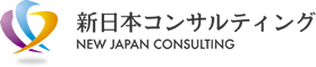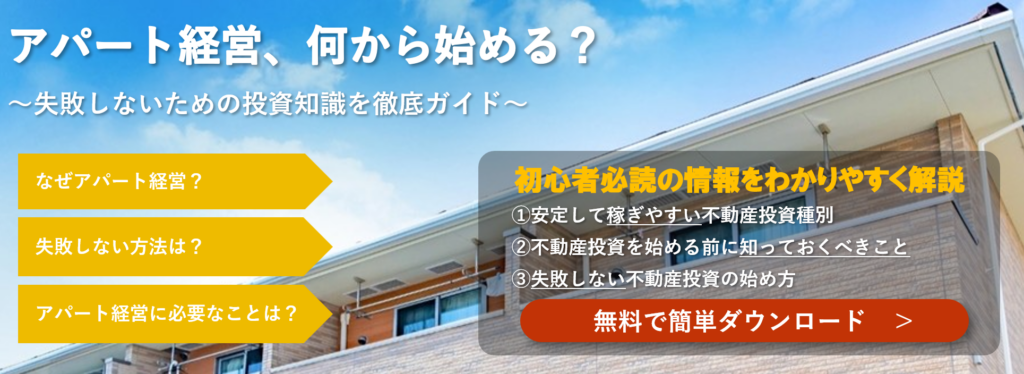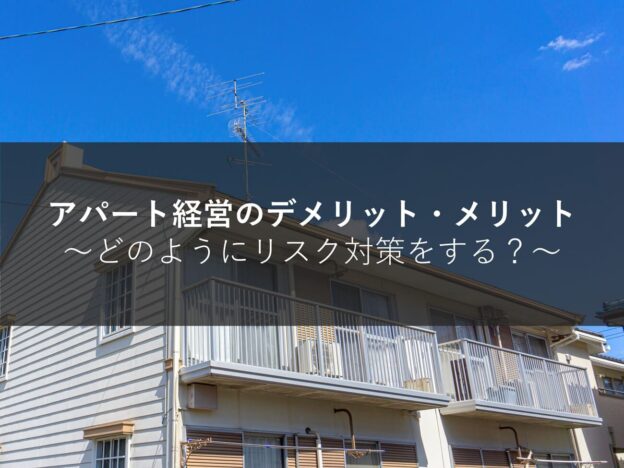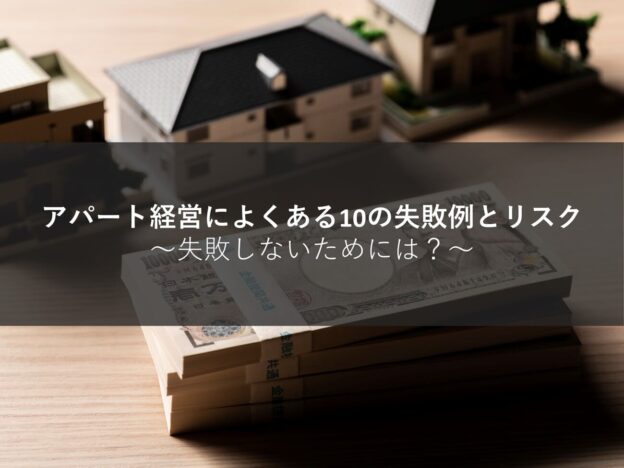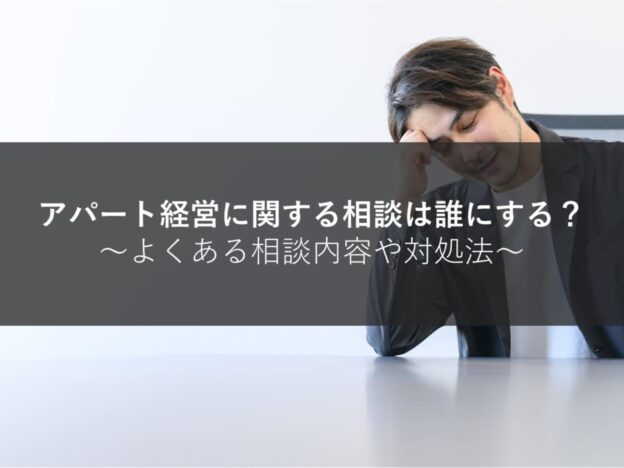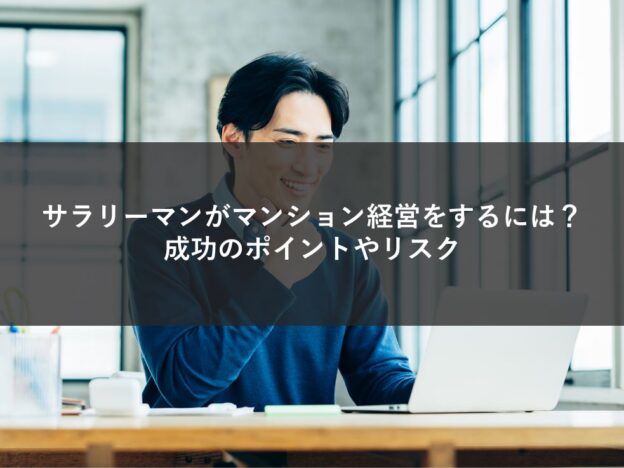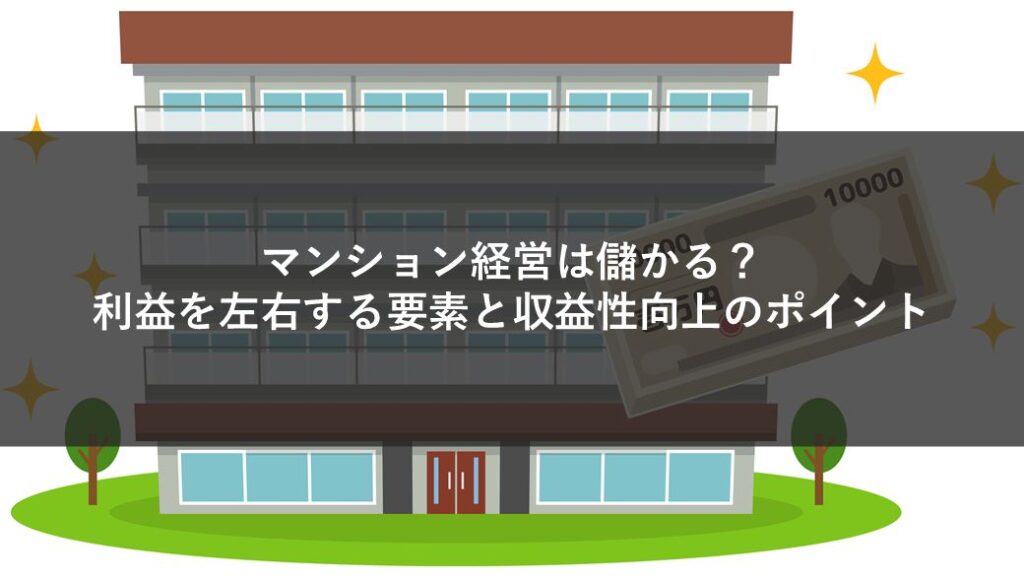
マンション経営は、安定した不動産投資の選択肢として注目を集めています。しかし、「儲かる」とも「儲からない」とも言われることがあり、マンション経営を始めたいものの不安で行動に移せていないという人も多いのではないでしょうか。マンション経営の「儲け(=利益)」はさまざまな要因が影響し合っており、儲かるマンション経営を実現するには、どうすれば利益が出るかをしっかり理解する必要があります。
そこで本記事では、マンション経営における「儲かる」の定義や、利益を左右する要素、そして利益を増加させるポイントについて詳しく解説します。マンション経営の成功に欠かせない「利益」について知識を深め、長期的に収益性の高い経営を実現しましょう。
目次
マンション経営において「儲かる」の定義は?

マンション経営で「儲かる」とはどのような状態を指すのでしょうか。その定義と判断基準を見ていきましょう。
マンション経営において「儲け」とは
マンション経営における「儲け」は、家賃収入から経営に必要な支出を差し引いた後の利益を指します。この利益は、投資対効果を判断するうえで重要な指標となります。支出には主に、マンションの購入費やローン返済費、管理委託費、各種税金、修繕費などが含まれます。これらの費用を適切に管理し、収支バランスを保つことが、安定した利益を生み出す鍵となります。
マンション経営で「儲かっている」状態とは
マンション経営の目的によって「儲かっている」状態の定義は異なります。例えば、複数の物件に投資し、ポートフォリオを入れ替えながらマンション経営を拡大させたいオーナーであれば、保有する一部のマンションを手放すときに、その物件単体での収支が大きくプラスになっていれば「儲かっている」状態と言えるでしょう。また、規模は小さくてもコツコツ地道に資産形成を行いたいオーナーにとっては、マンション経営全体で自身が目標とする利益を確保できるようになれば「儲かっている」状態と言えるかもしれません。このように、マンション経営の目的によって「儲かっている」状態の定義は変わるため、まずは自身のマンション経営の目的を明確にすることが重要です。
マンション経営の利益を左右する主な要素

マンション経営の収益性はいくつかの要素が影響し合っています。ここでは、マンション経営の利益に関わる要素として、以下の4つを解説します。
- 家賃設定
- 不動産投資ローンの借入条件
- マンションの性能
- マンションの立地
家賃設定
家賃設定はマンション経営の利益を左右する重要な要素です。家賃の額は入居率に直接影響するため、慎重に決定する必要があります。
例えば市場相場を無視して高額な家賃を設定すると、入居者が集まりづらく空室リスクが高まります。そのため、適切な価格設定により高い入居率を維持することが、安定して利益を得るためのポイントとなります。地域の相場や物件の特性を考慮し、競争力のある家賃を設定しましょう。
また、定期的に家賃の見直しを行うことも大切です。市場動向や物件の価値変化に応じて適切に調整することで、長期的な収益性を確保できます。
不動産投資ローンの借入条件
ローンの金利や返済期間などの借入条件は、マンション経営の利益に大きな影響を与えます。わずかな条件の差であっても、高額な借り入れを行う場合は支払総額に大きく響きます。
例えば、返済期間30年で1億円を借り入れる場合、0.1%の金利差でも、合計で150万円以上の利息差が生じます。そのため、金利交渉や金融機関の比較検討は非常に重要です。
また、返済期間を長くすると月々の返済負担が軽減され、手元の利益を確保しやすくなります。ただし、長期返済は総支払利息が増加するため、バランスを考慮して決定する必要があります。
マンションの性能
建物の性能を高めることは、長期的な資産価値の維持につながります。耐震性、断熱性、防音性などの性能が優れたマンションは、時間が経過しても価値が下がりにくい傾向にあります。そのため、将来の売却時に高値で取引される可能性があり、マンション経営の収益性にも寄与するでしょう。
また、入居者にとっても性能の高さは大きなメリットです。例えば、高い耐震性は安心感につながり、優れた断熱性や防音性は日常生活の快適さを向上させます。これらの要素は入居者の満足度を高め、長期入居や空室期間の短縮につながります。結果として、安定した家賃収入と低い空室率を実現でき、収益性の向上に役立ちます。
マンションの立地
立地条件は、家賃収入の安定性に大きく影響します。駅近や商業施設、学校の近隣など、利便性が高い場所は一般的に入居率が安定しやすい傾向にあります。しかし、単に現在の人気エリアを選ぶのでなく、将来の需要変化を見越した選択が重要です。例えば、再開発計画の有無や人口動態の変化など、長期的な視点での分析を行ったうえで、購入するマンションを選ぶと良いでしょう。
マンション経営が「儲からない」と言われる理由は?
マンション経営が「儲からない」と言われる背景には、社会的な課題やマンション経営の特性が関わっています。マンション経営を成功させるには、これらを理解して対策を講じることが重要です。
人口が減少しているため
日本の人口減少は、マンション経営の収益性に影響を与える大きな要因の一つです。人口が減少すると相対的に賃貸需要が減り、空室率が上昇するリスクが高まります。空室率の上昇は家賃収入の減少につながり、結果的に利益を圧迫します。
しかし、人口減少が必ずしも利益の減少に直結するとは限りません。例えば、単身世帯や核家族の増加により、世帯数が増加している地域もあります。このような地域では、小型のマンションへの需要が高まる可能性があります。したがって、マンション経営を長期的に安定させるには、人口動態だけでなく、世帯構成の変化や地域特性を考慮した戦略が必要です。
入居者の維持が難しいため
築年数が経過するにつれて、マンションの入居者維持が難しくなる傾向があります。これは、新築物件との競争や、設備の陳腐化などが要因です。
長期的に経営を続けるほど、入居者の需要低下や退去者の増加リスクが高まります。魅力の低い物件では、退去者が出た際に新たな入居者を見つけるのが困難になる可能性があります。
この問題に対処するには、定期的なリノベーションや設備更新、魅力的な付加価値の提供など、継続的な物件の価値向上が重要です。また、長期入居者へのインセンティブの提供なども効果的な対策となります。
短期的に利益を出すのが難しいため
マンション経営は、短期的な利益を期待すると「儲からない」と感じやすい投資です。これは、初期投資額が大きく、投資回収に時間がかかるためです。多くの場合、マンション購入時に多額のローンを組むため、初期段階では返済負担が大きくなります。そのため、短期的には収支がマイナスになることも珍しくありません。
マンション経営は時間の経過とともにローン残高が減少し、徐々に収益性が向上していくビジネスモデルです。短期的な利益にとらわれず、10年、20年といった長期スパンで収益性を評価することが大切です。
定期的な修繕が必要になるため
マンションの価値を維持するには定期的な修繕が不可欠です。加えて、一定の築年数が経過したタイミングで大規模修繕を行う必要があります。これらの修繕費用は、経営の収益性に大きな影響を与えます。
例えば、外壁の塗り替えや設備の更新など、大規模修繕には多額の費用がかかります。また、築年数が進むほど修繕の頻度や規模が大きくなる傾向があります。そのため、これらの費用を適切に見積もり、計画的に積み立てを行うことが重要です。また、日常的なメンテナンスを徹底することで、大規模修繕の周期を延ばし、コストを抑える工夫も必要になります。
災害リスクがあるため
火災、地震、台風などの災害は、マンション経営に大きなリスクをもたらします。災害によって建物に損傷が生じた場合は、修繕が発生したり、最悪のケースでは建て替えが必要になったりします。これらのリカバリーにかかる費用は予期せぬ支出となり、経営の収益性を大きく低下させる要因になるでしょう。災害リスクに対処するためには、適切な保険への加入が求められます。また、耐震性能の高い物件を選択することも、リスク軽減の一つの方法です。
マンション経営で利益を増加させるポイント
マンション経営の収益性を高めるには、さまざまな角度からのアプローチが必要です。ここでは、利益を増加させるための重要なポイントとして、以下9つを解説します。
- マンションの立地にこだわる
- マンションの性能や設備にこだわる
- 利回りのシミュレーションを行う
- 空室対策を行う
- リスクに備えて保険に加入する
- 信頼できる不動産会社(管理会社)に管理を委託する
- 入居者の審査を慎重に行う
- 税金対策を行う
- マンション経営のプロからサポートを受ける
マンションの立地にこだわる
利便性の高い立地を選ぶことは、入居率の安定化と家賃収入の確保に直結します。そのため物件購入前には、周辺環境を徹底的に調査することが重要です。例えば、駅からの距離、商業施設や学校の有無、治安の良さなどが重要な要素となります。また、競合物件の状況や将来の再開発計画なども考慮に入れる必要があります。
マンションの性能や設備にこだわる
入居者が安心・快適に住める高性能・高機能なマンションを取得することで、長期的な入居率の安定化が期待できます。例えばオートロックや宅配ボックス、浴室暖房乾燥機などの設備は、入居者のニーズに応えるうえで効果的です。ただし、高性能な物件は修繕リスクやランニングコストが上がる可能性もあるため、バランスを考慮する必要があります。
築古マンションの場合、リノベーションを行うことも効果的な選択肢です。既存の物件の良い部分を生かしつつ流行のデザインや設備を取り入れることで、新築マンションとは異なる魅力を生み出し、差別化によって競争力を高められるでしょう。
利回りのシミュレーションを行う
マンション経営を始める際は、綿密な収支計画を立て、利回りのシミュレーションを行うことが大切です。利回りとは、投資額に対するリターン(利益)の割合を示す指標です。事前に利回りのシミュレーションをすることで、運用時の実際の利回りと比較し、想定よりも下回っている際にどこに課題があるかを分析しやすくなります。
シミュレーションを行う際は、類似条件の物件を参考に、現実的な目標利回りを設定します。ただし、短期的に高い利回りを追求するよりも、長期的に安定した経営を目指し、徐々に目標利回りに近づけていくことを意識すると良いでしょう。
空室対策を行う
空室は直接的に収益を減少させるため、効果的な対策が欠かせません。現実的には常時満室を維持することは難しいため、空室期間をいかに短縮するかがポイントとなります。対策としては、物件の魅力向上、適切な家賃設定、効果的な広告宣伝などが挙げられます。また、長期的に空室が解消されない場合は、民泊やマンスリーマンションとしての活用も検討すると良いでしょう。
リスクに備えて保険に加入する
災害リスクに備えて、火災保険や地震保険への加入は必須です。これにより、不測の事態による経済的
負担を軽減できます。また、不動産投資ローンを利用する場合は、団体信用生命保険への加入も検討すべきです。これにより、万が一の際にローンが完済され、家族に資産を残すことができます。
信頼できる不動産会社(管理会社)に管理を委託する
管理会社の選択は、マンション経営の成否を左右し得る重要な要素です。管理会社のサービス品質は、入居者の満足度や長期入居に影響し、マンション経営の収益性にも関わります。
信頼できる管理会社を選ぶためには、管理実績やオーナーからの評判を十分に調査することが大切です。優れた管理会社は入居者対応やメンテナンス、家賃徴収などを適切に行い、オーナーの負担を軽減しつつ物件の価値を維持・向上させます。
入居者の審査を慎重に行う
家賃滞納リスクを最小限に抑えるため、入居者の審査を徹底することが重要です。一般的には年収や職業などの属性をもとに審査を行いますが、家賃を支払えるだけの支払能力があるか、素行や経歴など信頼性に問題がないかを総合的に判断するようにしましょう。また、賃貸保証会社の利用も有効な選択肢です。これにより、家賃滞納リスクを軽減しつつ、入居者の幅を広げることができます。
税金対策を行う
マンション経営で得た利益に対しては所得税や住民税などが課されます。課税対象となるのは、収入から必要経費を差し引いた金額です。マンション経営においては減価償却費や修繕費、管理委託費などの物件に対して直接的に発生する費用のほか、事業に用いる車両代や事務所の家賃といった費用も経費に含められる場合があります。どの程度の費用を経費にできるかはケースバイケースのため、税理士などの専門家のアドバイスを受けたうえで確定申告を行うと良いでしょう。適切に経費計上ができれば、課税所得を抑え、結果的に手元に残る資金を増やすことができます。
マンション経営のプロからサポートを受ける
マンション経営の収益性を高めるためには、プロのサポートやアドバイスを受けることが有効です。不動産投資の専門家は、物件選びや資金計画、法律面でのアドバイスから運用におけるサポートまで、幅広い場面で助けになってくれるでしょう。
経験の浅いオーナーであっても、プロのサポートによってマンション経営の多くの落とし穴を避け、効率的に収益を向上させることができます。信頼できるアドバイザーを見つけ、長期的なパートナーシップを築くことが、マンション経営の成功への近道となるでしょう。
マンション経営の悩みに関するご相談は新日本コンサルティングまで!
長期的に儲かるマンション経営を実現するためには、利益がどのように生まれるのかを理解し、収益性を高めるさまざまな工夫に取り組むことが重要です。しかし、マンション経営には多岐にわたる専門知識と経験が必要になるため、経験の少ないオーナーが独力で事業を成長させることは容易ではありません。そのため、経営に関するサポートが充実している会社をパートナー企業として選ぶことが非常に重要になります。賃貸管理や経営について長期間にわたって相談できるパートナーがいれば、さまざまな局面で適切なアドバイスを受けられ、安心して経営を進めることができるでしょう。
新日本コンサルティングは、マンション経営に関する豊富な経験と専門知識を持ち、物件選びから運営管理まで、マンション経営に関する総合的なサポートを提供しています。マンション経営に興味のある方は、ぜひ以下から気軽に資料請求やお問い合わせください。