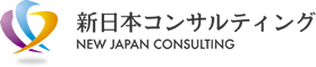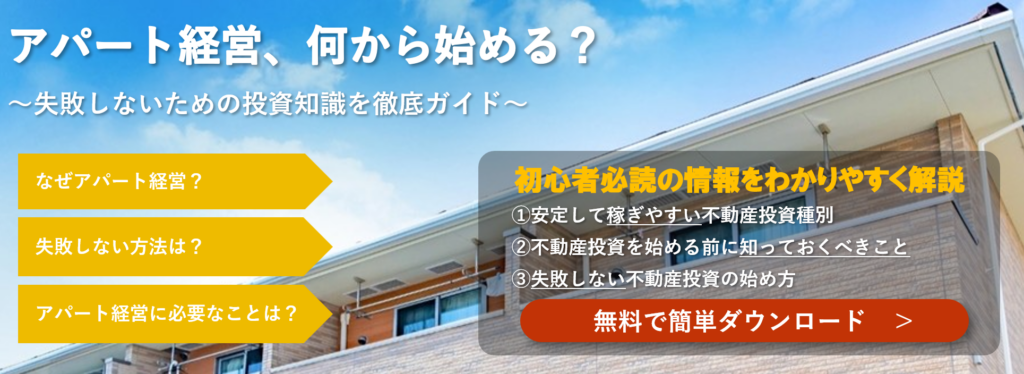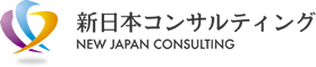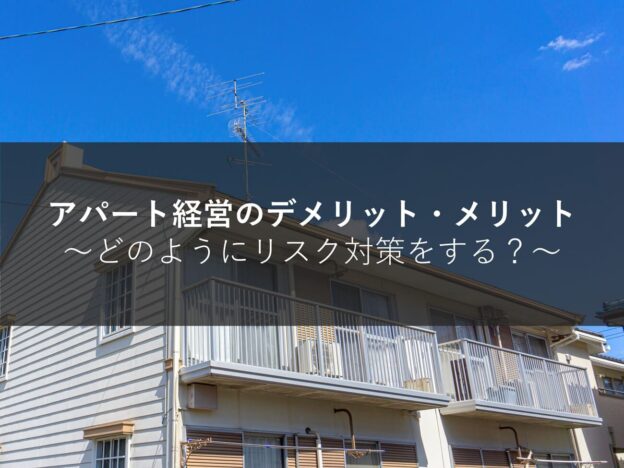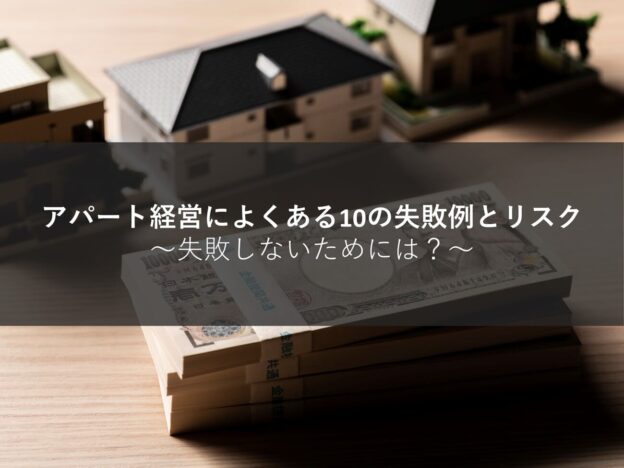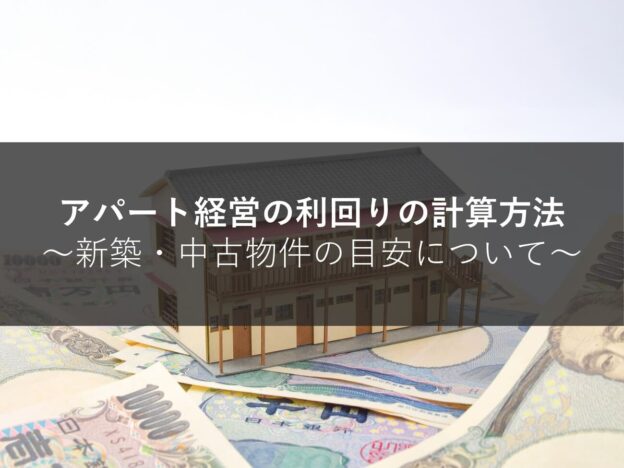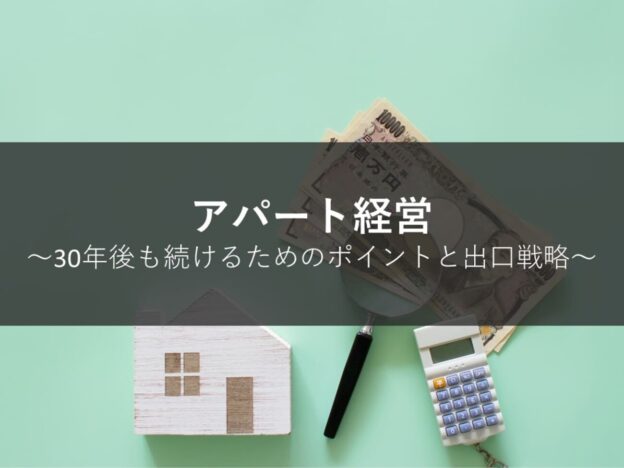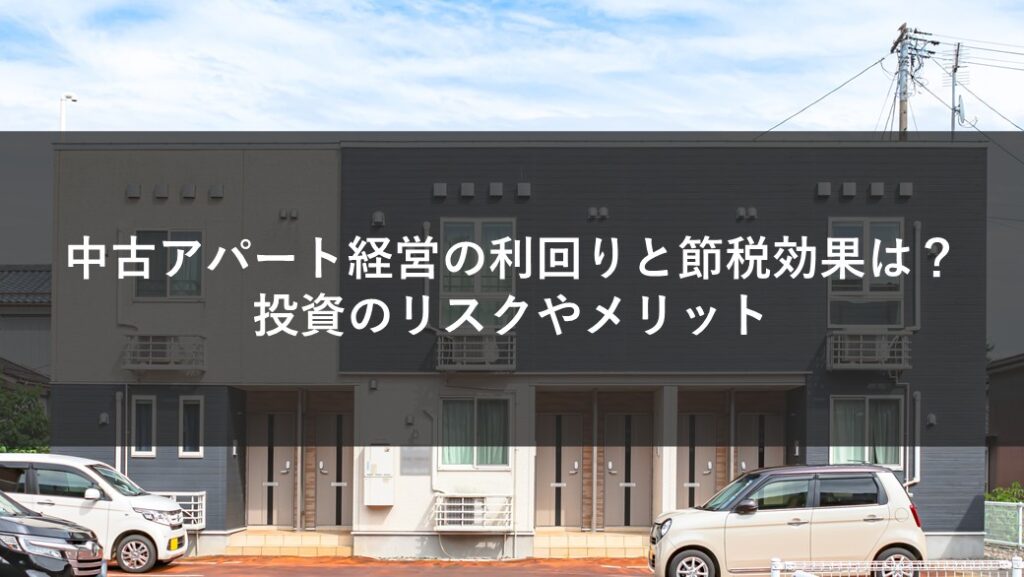
アパート経営に興味を持っている人の中には、中古物件を購入して投資を始めようとしている人もいるのではないでしょうか。中古のアパート経営は、初期投資を抑えつつ高い利回りを期待できる一方で、リスクや対処すべき課題も存在します。
この記事では、中古アパート経営の利回りやメリットとデメリットを解説し、どのようにすれば賃貸経営を成功させられるかを考えていきます。
中古アパート経営のメリット

中古のアパートを購入して行う賃貸経営にはいくつかのメリットがあります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。
- 初期費用を抑えやすい
- 利回りが高くなりやすい
- 既に建築されている物件を見て購入ができる
- 価格が下がりにくい
初期費用を抑えやすい
中古アパートは新築と比較すると、初期費用を抑えながら物件を購入することが可能です。これは、アパートの資産価値が築年数に応じて下がる傾向があることが影響しています。
あくまで目安ですが、物件の価値は築10年で1割程度、築20年で2割程度価格が下がると言われています。したがって、築年数が経った中古アパートの購入は、賃貸経営の初期費用で大きな割合を占める物件購入のコストを抑えやすくなります。
※ただし、エリアや建物の構造によっては、築10年で約2割程度、築20年で約3~4割程度下がることもあります。
利回りが高くなりやすい
アパート経営を始めるうえで大切な知識のひとつに「利回り」があります。利回りにはいくつか種類がありますが、そのうちの一つである表面利回りは、アパートの購入費用に対する1年間のインカムゲイン(家賃収入)の割合を指しています。中古アパートは新築アパートよりも安く購入できることが多いため、利回りが相対的に高くなる傾向があります。つまり、早い期間で投資にかかった費用を回収しやすいのです。
物件の築年数による利回りの違いを表にまとめました。
| 築20年以上 | 8~10% |
| 築10年~20年 | 6~8% |
| 新築や築浅 | 4~6% |
(注)利回りはアパートの建っているエリアや建物の構造によって大きく変わります
既に建築されている物件を見て購入ができる
中古アパートの大きな利点の一つに、実際に建っている物件を見て購入の判断ができる点が挙げられます。物件の状態や管理状況などを直接確認した上で購入の判断が可能です。さらに、過去の利回りや空室率などのデータを事前に把握できるのも中古物件ならではの特徴と言えます。
一方で新築アパートは完成前に購入するケースが多く、実際の建物を確認して購入を判断するのは難しいです。
価格が下がりにくい
築年数の経過による資産価値の変動は、新築より中古のほうが比較的緩やかです。つまり、同じ20年間でも新築アパートを買ったときと中古アパートを買ったときでは、中古アパートのほうが価格の下がり方が緩やかな傾向にあります。
新築アパートは、一定の築年数が経過するまでは資産価値が大きく下がり続けるのが一般的ですが、中古アパートはその急激な下落期を過ぎているため、価格の変動が少ないです。
つまり購入時と売却時の価格差が少ないため、万が一物件を手放すことになったとしても、中古アパートのほうが初期費用を回収しやすくなります。
中古アパート経営のデメリット
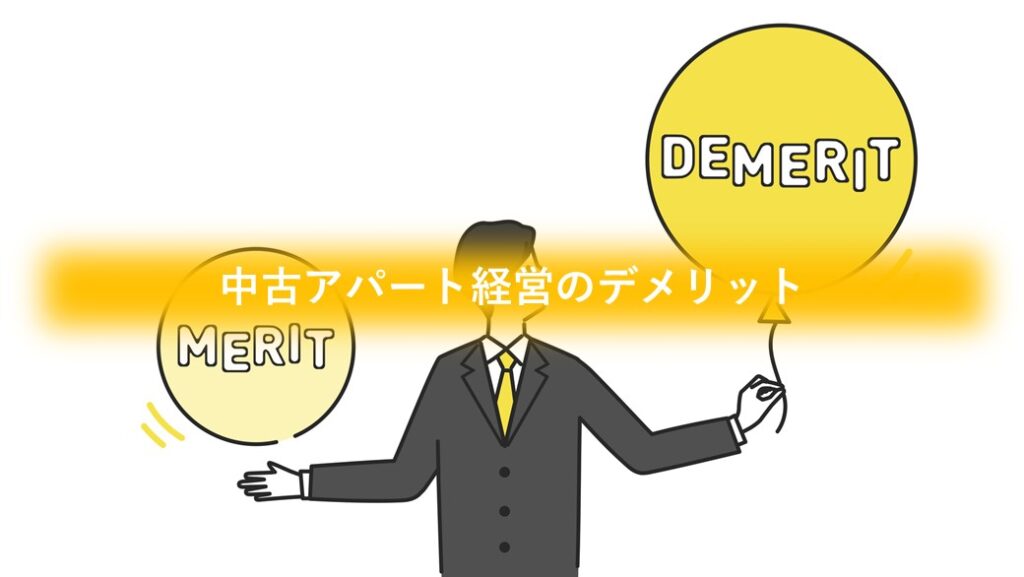
中古アパート経営には魅力的な面が多いものの、同時にいくつかのデメリットも存在します。具体的には以下のようなデメリットがあります。
- 新築物件以上に空室リスクへの対策が必要になる
- 修繕費用がかさみやすい
- トラブルのリスクがある
- 売却が難しい傾向にある
新築物件以上に空室リスクへの対策が必要になる
中古アパートより新築のアパートのほうが入居者からの人気が高い傾向にあります。したがって、あまりにも築年数が経っているアパートは入居者を集めにくく、空室リスクが高くなる可能性があります。
確かに、アパートは一棟に複数の部屋があるため空室リスクは分散しやすいです。しかし空室が多く出たり、長く続いてしまったりする場合は、融資の返済にも影響してしまいます。
また、将来的にアパートを売却する際も、空室期間が長い点を指摘されて交渉が不利になることがあります。物件の買い手は、過去の空室率も判断材料としているため、長期間の空室は物件の価値を大きく下げてしまう可能性があるのです。
修繕費用がかさみやすい
中古アパートは築年数が経っているため、新築の物件に比べて経年劣化が起きていることが多く、修繕費用がかさみやすい傾向があります。入居者を確保するには、建物の価値を保つ必要があるため、定期的な建物のメンテナンスや改修が欠かせません。特に、屋上防水や外壁塗装、配管関係、そのほか耐震性に関わる部分は修繕費用が高くなりやすいです。
また、昭和56年5月以前に建築確認を取得している旧耐震物件はより注意が必要になります。これらの物件は修繕費用が高額になるリスクが高いです。
後々になって予想外の修繕費が発生しないためにも、一級建築士などの専門家に建物のリスクを判定してもらうことをおすすめします。
トラブルのリスクがある
引き継いだ中古アパートが、既に住民トラブルを抱えていた場合、対処が必要になることもあります。例えば、騒音問題や駐車場の使用ルールをめぐるトラブルなどです。こうしたトラブルを放置していると入居者の退去につながります。
このような事態に対処するためにも、契約前に問題を抱えていないかチェックしたり、過去にトラブルがなかったか売主に尋ねたりすると良いでしょう。また、管理会社に物件の管理を依頼するなら、連携を密に行っておくことも大切です。定期的な入居者アンケートの実施や、苦情への迅速な対応フローの構築など、トラブルの早期発見と解決に向けた体制を整えることが求められます。
売却が難しい傾向にある
アパート経営の出口戦略において、大きな利益獲得や損切りを図る「売却」は重要な選択肢の一つです。しかし中古アパートは売却したいタイミングで買い手が見つかりにくい一面もあります。
これは、中古物件が金融機関からの評価が低い傾向にあり、融資の審査が厳しめになるためです。買い手側も中古アパートを購入するための融資を用意するのが難しく、結果的に買い手が見つかりづらい状況になっています。
将来的にスムーズにアパートを売却するには、定期的なメンテナンスや空室対策を実施し、資産価値の高い状態を維持しながら経営を続けることが大切です。また、売却を視野に入れる場合は、早い段階から不動産会社と相談し、市場動向を把握しておくことも重要と言えるでしょう。
中古アパート経営の始め方
中古アパート経営を始めるにあたっては、計画的なアプローチが不可欠です。ここからは経営を始めるまでの具体的な手順を解説します。
STEP1.アパート経営の目的と方針の決定
アパート経営を行う際は、投資の「目的」と「方針」を明らかにしておくことが重要です。これは、目的に一致しない物件を選んでしまうリスクを回避するためです。
例えば、老後の安定収入を目的とするなら、長期的な視点で安定した家賃収入が見込める物件を選ぶべきでしょう。一方、短期的な資産運用を目的とするなら、売却益を見込める物件を選ぶことが多いです。
そして、自己資金の額や借入可能額、リスク許容度なども考慮に入れて、具体的な投資方針を決定します。例えば、「どのエリアの物件を対象とするか」「築年数や構造の許容範囲」「想定する利回り(表面利回り・実質利回り)」「管理は自主管理か委託か」など、複数の判断基準を明確に設定します。
STEP2.物件の情報収集と調査
続いて、購入する物件の情報収集と調査を行います。不動産会社や不動産投資セミナーなどを通じて、幅広く情報を集めます。
情報収集の際は、物件の実地調査も欠かずに行いましょう。外観や共用部分の状態、個別の部屋の内装(入居者がいない場合)、設備の状況などは、目で見て確認することが重要です。
加えて周辺の家賃相場や将来的な開発計画なども調べておくと良いでしょう。これらの情報を総合的に分析することで、投資価値の高い物件を見極められます。
STEP3.経営方法・資金計画の策定
アパートの経営方法は、自分で物件を管理する自主管理と管理会社への委託の2通りがあります。自主管理の場合は委託費を抑えられますが、時間と労力がかかります。物件管理は突発的かつ迅速な対応が求められることもあるため、管理会社への委託を選ぶ人が多いです。
資金計画を立てる際は物件の購入資金やリフォーム費用、運転資金などを詳細に算出します。この計画は融資を受ける際にも必要になります。初めて賃貸経営を行う人は、不動産会社の担当者や不動産コンサルタントなどからアドバイスを受けて進めることが多いです。
STEP4.ローンの検討と借入手続き
物件の購入資金が自己資金だけで足りない場合は、金融機関にローンを申し込みます。まずは、どの金融機関で、どのような条件のローンを利用するかを検討します。金利のタイプ(固定金利・変動金利)、返済期間、返済方法(毎月どれくらい返すか)などを比較した上で、無理のない返済計画を立てましょう。
次に、ローンの事前審査を申し込みます。審査では、申込者の収入や借入状況、購入予定の物件の内容などが審査されます。審査に通過したら、正式に融資を申し込みます。
STEP5.物件購入の契約・決済
計画を立てたら物件を購入する準備を進めます。物件を購入する際は売買契約書の内容を細かく確認することがとても重要です。
特に注意すべき点は、物件の引き渡し時期、代金の支払い方法と時期、既存の賃貸借契約の扱いなどです。特に中古アパートを購入する際は物件の状態に対する特記事項を確かめましょう。例えば、雨漏り・シロアリ被害・設備の故障などの有無、境界の未確定箇所、建築基準法に適合しているかどうか、過去に無許可の増改築が行われていないかなどです。
STEP6.リフォームや設備改修を行う
入居率を上げるため、あるいは安全に住めるようにするためにリフォームや設備改修を行います。外壁の塗り替え、水回りの設備更新、内装のリニューアルなどが一般的な改修項目です。特に、キッチンやバスルーム、トイレなどの水回り設備は入居者の関心が高い部分であり、より使いやすくなるよう改修することで、物件の魅力が向上します。また、断熱性能の向上や省エネ設備の導入など、長期的な維持費の削減につながる改修も検討しましょう。
中古アパート経営で利益を出すためのポイント
中古アパート経営で安定した利益を上げるには、いくつかの重要なポイントがあります。
- 立地の良い物件を選ぶ
- 状態の良い物件を選ぶ
- 物件の入居状況を確認する
- 売買契約の内容をしっかりと確認する
一つずつ詳しく解説します。
立地の良い物件を選ぶ
立地の良い物件は、築年数が経っていても入居者が集まりやすいという利点があります。駅近や周辺にスーパーやコンビニがあるなど、生活利便性の高い場所は常に需要が高いです。こうした立地の良い物件が市場に出やすい点も、中古物件の特徴でもあります。
ただし、立地の良い物件は魅力的な分、価格も高くなりやすいため、購入する際は価格と収益性のバランスを考慮することが重要になります。
状態の良い物件を選ぶ
物件の状態が良ければ、購入後の修繕やリフォームにかかる費用負担を抑えられるため、初期費用を軽減できます。特に建築から5年以内の築浅物件は人気も高く、入居者を集めやすいです。しかし、築年数の経過した中古アパートでも、室内・外観ともに状態が良く、家賃が適正なら入居者も集まりやすい傾向にあります。
中古アパート購入の際は建物の外壁や共用部、室内の状態などを必ず現地で確認しましょう。現地確認の際は外壁の劣化状況、配管の状態などをチェックします。
物件の入居状況を確認する
中古アパートは、入居者が既にいる状態で売買されることが一般的で、これをオーナーチェンジ物件と呼びます。オーナーチェンジ物件では、原則として現行の賃貸借契約が新たな所有者に引き継がれます。契約書の内容を確認し、賃料・敷金・特約条項(退去時の原状回復など)について事前に把握しておくことが重要です。
長期入居者の有無、家賃の滞納履歴、入居者の属性(学生、社会人、ファミリー)などを調べれば、将来の収益性や管理の難易度をある程度予測できるためです。
また、現在の入居率や過去の推移も購入にあたっての判断材料になります。安定した高入居率を維持している物件は、立地や物件の魅力が高いことを示しています。一方で、空室が多い物件の場合は、その理由を詳しく調査し、改善の余地があるかどうかを見極める必要があるでしょう。
売買契約の内容をしっかりと確認する
不動産に関係する契約の締結前には「重要事項説明書(35条書面)」について、不動産取引の専門家である宅地建物取引士から説明を受けることが法律で定められています。
具体的には欠陥が発覚した場合の対応(契約不適合責任)や代金の支払い時期、物件の引き渡し時期、敷金や家賃の取り扱い、抵当権の抹消などの説明を受けます。
特に契約不適合責任は重要なため、念入りにチェックする必要があります。引き渡し後に発見された欠陥に対する売主の責任範囲や期間を明確に確認しておかないと、後々重大なトラブルにつながる可能性があるためです。
中古アパート経営は慎重な計画立てが成功のコツ
今回は中古アパート経営に関する内容を解説しました。中古アパートは、初期投資を抑えつつ高い利回りを期待できる投資方法です。しかし、新築物件と異なるリスクも存在します。したがって立地や物件の状態、入居状況などの調査や、リスクを想定した資金計画を立てることが重要になってきます。また、リフォームや設備改修を通じて物件の価値を高め、長期的な視点で経営を行うことが求められます。中古アパート経営に興味をお持ちの方は、専門家のアドバイスを受けながら、戦略を立てることをおすすめします。
新日本コンサルティングは、アパート経営に関する豊富な経験と専門知識を持ち、物件選びから運営管理まで、アパート経営に関する総合的なサポートを提供しています。アパート経営に興味のある方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。