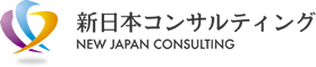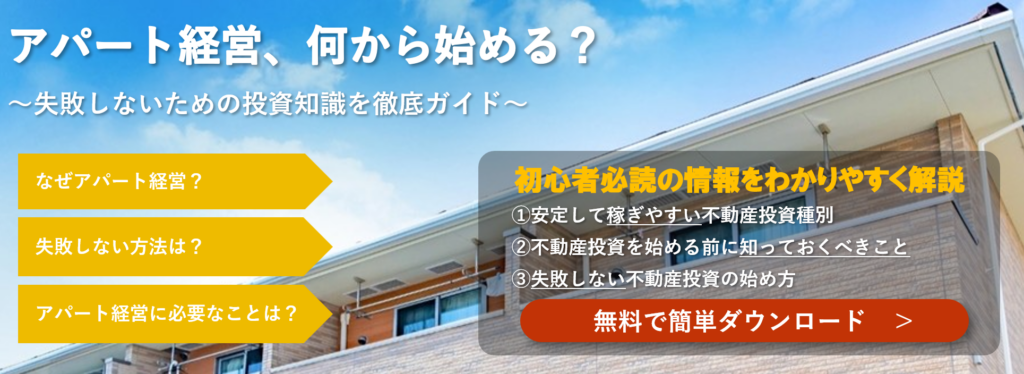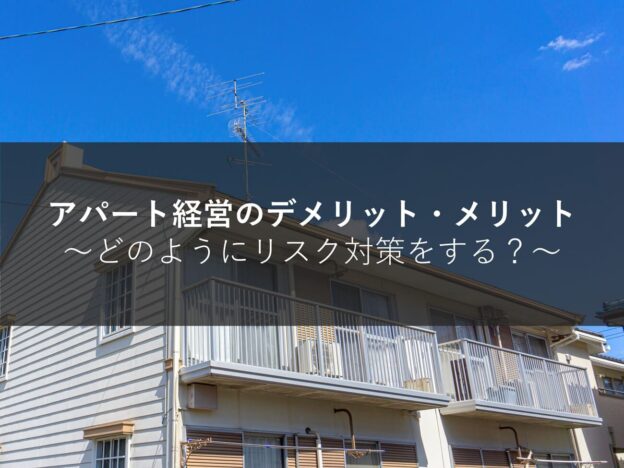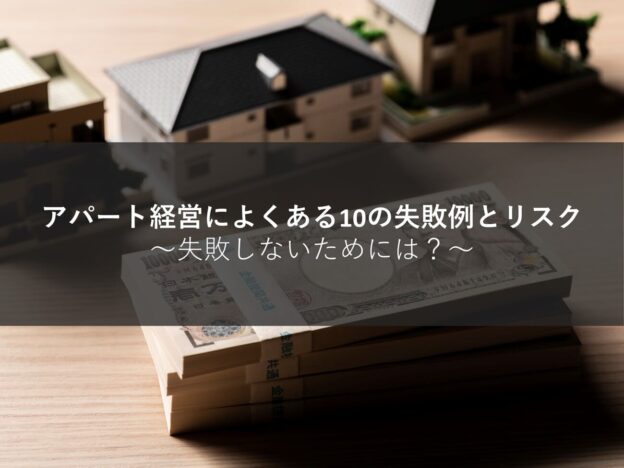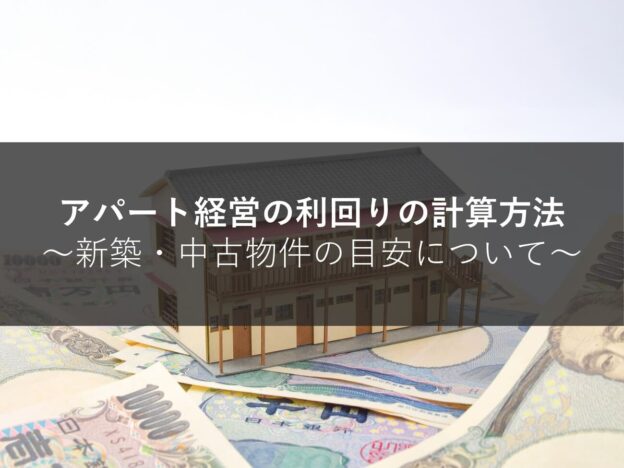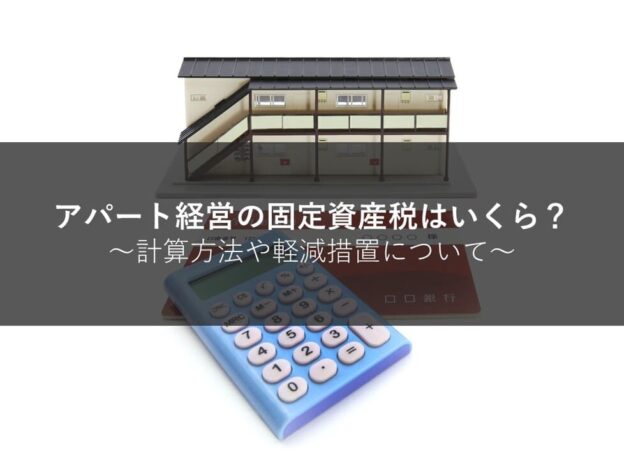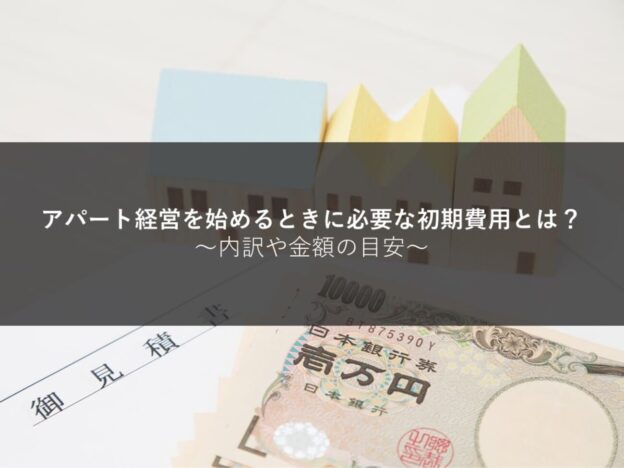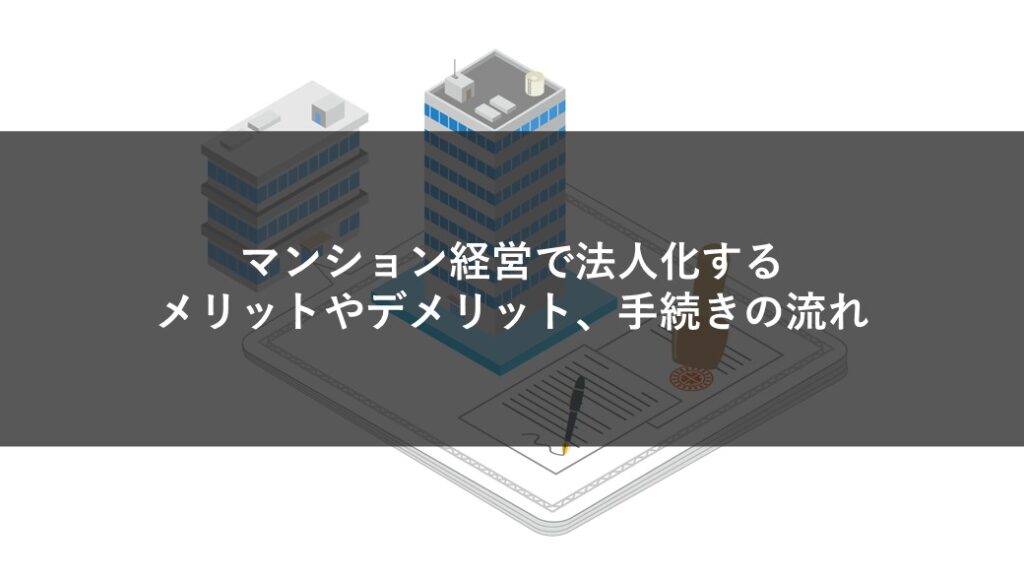
「マンション経営を法人化するメリットやデメリットは?」
「法人化はどのように進めれば良い?」
上記のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?
個人として行っているマンション経営を法人化することは、税金や経費の面で多くのメリットをもたらす可能性があります。しかし、法人化には多くの手続きや新たな費用負担が伴うことから、適切なタイミングでの実施が求められます。
本記事では、マンション経営を法人化するメリットやデメリット、手続きの流れについて詳しく解説します。
目次
マンション経営における法人化の概要
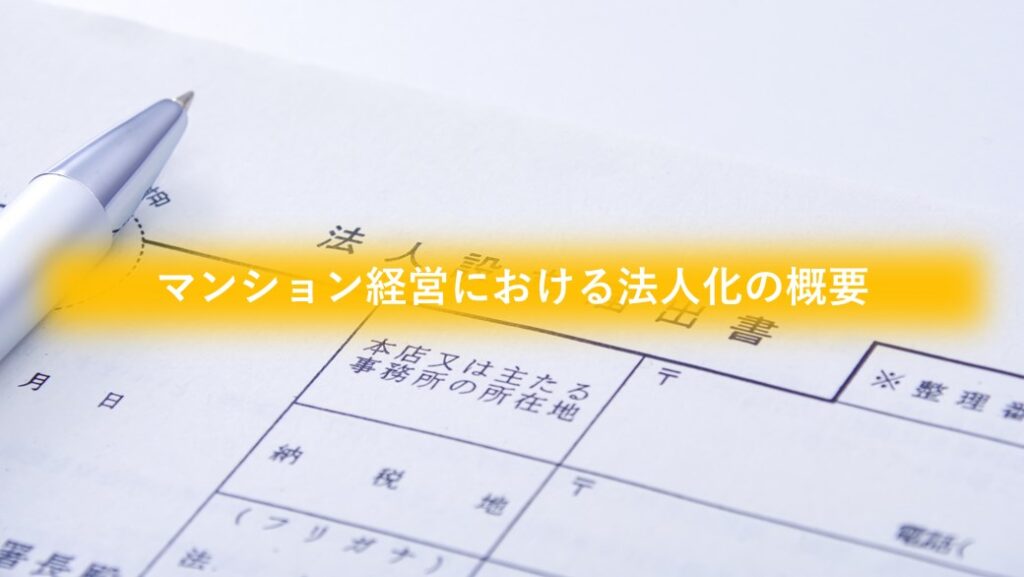
マンション経営において法人化は、税金対策や資産管理の面で大きな影響を与える重要な選択です。ここでは、法人化の概要と適切なタイミングの目安について解説します。
マンション経営の法人化とは
マンション経営の法人化とは、個人で行っていたマンションの所有と管理を法人名義に変更し、会社として運営することを指します。法人化により、不動産所得は個人ではなく法人のものとなり、課税方法や経営管理の仕組みが大きく変わります。法人化は、賃貸経営の規模拡大や相続対策等の税負担の軽減などを目的として検討されることが多いです。
法人化するタイミングの目安
マンション経営の法人化を検討する際の指標として、課税所得額があります。一般的に、マンション経営からの課税所得が900万円~1,000万円程度になるタイミングで、法人化を検討したほうが良いとされています。これは、個人の所得税率と法人税率の違いに起因します。
個人の場合、所得税は累進課税制度が適用され、所得が増えるほど税率が上がります。例えば課税所得が695万円~900万円未満の場合は所得税率が23%ですが、900万円以上になると33%となります。一方、法人税率は原則として一律であり、中小企業の場合は年800万円以下の所得に対して15%、それを超える部分に23.2%の税率が適用されます。
したがって課税所得が900万円以上になると、個人で経営を続けるよりも法人化したほうが、税負担が軽くなる可能性が高くなります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の判断には個々の状況や将来の計画を考慮する必要があります。
参考:「No.2260 所得税の税率」(国税庁)
参考:「No.5759 法人税の税率」(国税庁)
マンション経営を法人化するメリット

マンション経営の法人化には、税制面や資金面などさまざまなメリットがあります。ここでは主要なメリットとして以下4点を解説します。
- 経費計上できる範囲が広がる
- 長期間にわたり欠損金の繰越ができる
- 資金調達がしやすくなる
- 贈与税・相続税対策になる
経費計上できる範囲が広がる
法人化することで、個人事業主よりも広範囲の費用を経費として計上できるようになります。これは、法人の不動産所得に対する課税対象額を減少させ、結果的に税負担の軽減につながる重要なポイントです。具体的には、自分自身や従業員として働く家族の給与・賞与、また自宅を社宅として扱うことで、住居費も経費として計上できる可能性があります。
長期間にわたり欠損金の繰越ができる
法人化のメリットの一つに、欠損金の繰越期間の長さがあります。欠損金とは事業年度の損失(税務上の赤字)を指し、この損失を翌年度以降の利益と相殺することを繰越と呼びます。
法人の場合、欠損金の繰越期間は最長10年間となっています。一方、個人事業主(青色申告事業者)の場合は3年間しか認められません。この違いは、長期的な不動産経営において大きな影響を与える可能性があります。
例えば、大規模な修繕や改装を行った年に大きな損失が発生した場合、法人であればその損失を10年間にわたって将来の利益と相殺できます。これにより、長期的な視点での税務計画が可能となり、安定した経営基盤を築きやすくなります。
参考:「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(国税庁)
参考:「No.2070 青色申告制度」(国税庁)
資金調達がしやすくなる
法人化によって、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性があります。これは、法人としての社会的信用が個人よりも高く評価されることがあるためです。
銀行は融資の際、借り手の信用力を考慮します。法人化することで、財務諸表や事業計画書などの客観的な資料を提示しやすくなり、金融機関との交渉がスムーズになることがあります。また、法人名義での不動産所有は、個人名義よりも安定性があると見なされることもあります。
ただし、新設したばかりの法人は実績が不足していると判断され、融資の審査が厳しくなる場合もあるため注意が必要です。このような場合は、個人保証を求められたり、担保設定が必要になったりすることもあるため、事前に金融機関と十分に相談を行いましょう。
贈与税・相続税対策になる
法人化は将来の相続や贈与を見据えた税務対策としても有効です。特に、相続人を役員として登用して役員報酬を支払うことで、贈与税の発生を抑えつつ財産の移転を行えます。
具体的には、相続予定者を会社の役員として雇用し、適正な報酬を支払います。この報酬は会社の経費として計上され、相続人にとっては給与所得となります。給与所得は贈与税の対象外であるため、実質的な財産移転を行いながら、贈与税を回避することができます。
また、このような方法で財産を徐々に移転することで、将来の相続時の相続財産を減少させる効果が期待できます。相続税は相続財産の額に応じて税率が上昇するため、事前に財産を減らしておくことで、相続税の負担を軽減させられるでしょう。
さらに、法人化して株式を相続人に分配するなど、柔軟な相続対策を立てやすくなります。これにより、スムーズな事業承継や相続トラブルの防止にもつながります。
マンション経営を法人化するデメリット
法人化には多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。ここでは主な注意点として以下3点を解説します。
- 設立と運営にコストがかかる
- 社会保険の加入義務がある
- 税務調査の確率が上がる
設立と運営にコストがかかる
マンション経営を法人化すると、設立費用と運営費用という二つの主要なコストが発生します。これらのコストが経営を圧迫する可能性もあるため、慎重に検討が必要です。
設立時には、登録免許税や定款の認証費用、収入印紙代、司法書士費用などが必要となります。具体的な金額は会社の形態や資本金によって異なりますが、一般的に数十万円程度の初期費用が発生すると考えておきましょう。
これに加えて、法人の維持管理にも継続的なコストがかかります。具体的には事務所の家賃や水道光熱費、税理士・会計士への顧問料、社会保険料(従業員を雇用する場合)、法人住民税の均等割などが挙げられます。
特に注意が必要なのは、法人住民税の均等割です。これは会社の収益の有無にかかわらず、毎年定額で支払う必要があります。つまり、赤字経営であっても支払い義務が生じるため、経営状況が芳しくない場合は大きな負担となる可能性があります。
社会保険の加入義務がある
法人化すると、一定の条件を満たす場合に役員や従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務が生じます。これは従業員の福利厚生の観点からは望ましいものの、会社にとっては新たな費用負担となります。
社会保険料は従業員の給与に応じて計算され、その半額を会社が負担します。これらの費用は、従業員一人当たり数万円の追加コストとなり、複数の従業員を雇用する場合は大きな負担となるでしょう。
税務調査の確率が上がる
法人化により、個人事業主だった場合と比較して税務調査を受ける可能性が高くなります。これは、法人のほうが個人よりも取り扱う金額が大きく、取引も複雑になる傾向があるためです。
税務調査では、会社の帳簿や領収書、契約書などの確認が行われます。特に注意が必要なのは以下の点です。
1. 経費の適正計上:個人的な支出を会社の経費として計上していないか
2. 役員報酬の妥当性:過大な役員報酬を支払っていないか
3. 取引の実在性:架空取引や循環取引がないか
4. 消費税の適正処理:非課税取引と課税取引の区分が適切か
税務調査への対応には、日頃からの適切な会計処理と書類の保管が不可欠です。また、税理士などの専門家のサポートを受けることで、リスクを軽減し、スムーズな対応が可能になるでしょう。
マンション経営を法人化する際のポイント
法人化を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、そのポイントとして以下4点について解説します。
- マンションの建物だけを法人所有にする
- 設立時に株主や役員を決める
- 役員報酬を決める
- 勤めている会社の就業規則を調べる
マンションの建物だけを法人所有にする
マンション経営を法人化する際、建物のみを法人所有とし、土地は個人所有のまま法人に貸し出す方式を採用することを検討しましょう。
土地と建物の両方を個人から法人に売却すると、土地の価値が上昇しているために譲渡益が大きくなる可能性があり、税負担が増える懸念があります。そこで土地は個人所有のままにして、法人に貸し出す方式を取れば、土地部分の譲渡益による税金の発生を防げるため、法人化の際の負担を減らすことができるのです。
ただし土地を法人へ貸し出す際、土地の権利金や地代を適正な金額に設定する必要があります。無償または著しく低額での貸与は、税務上、無償譲渡と見なされる可能性があります。これを避けるためには、近隣の相場を参考に適切な権利金・地代を設定し、確実に支払いを行うことが重要です。
設立時に株主や役員を決める
法人設立の際、株主と役員の構成を慎重に検討することが重要です。特に、相続対策を視野に入れている場合は、家族を株主や役員に加えましょう。適切な株主・役員構成を事前に設計しておくことで、相続対策に加えて円滑な事業承継、さらには経営の安定化にもつながります。ただし、未成年者などは役員として認められない場合があるため、法律に基づいた適切な人選が求められます。また、名目上の役員は避け、実際に経営に関与する人物を選任するよう心がけましょう。
役員報酬を決める
法人化する際には、役員報酬を適切に設定することが重要です。役員報酬は法人の経費として計上できるため、税負担の軽減に寄与します。ただし、役員報酬の金額は市場の相場や会社の業績、貢献度合いに応じて決定する必要があります。過度に高い報酬にすると税務署からの指摘を受ける原因になり得るため、適切な金額を設定しましょう。
勤めている会社の就業規則を調べる
法人化を検討する際には、現在勤めている会社の就業規則を確認することが重要です。特に、副業が禁止されていないかを確認する必要があります。就業規則に違反して副業を行うと、最悪の場合、懲戒解雇などの深刻な結果を招く可能性があります。そのため、法人化を進める前に、必ず勤務先の人事部門や上司に相談し、適切な手続きを踏むようにしましょう。場合によっては、勤務先との良好な関係を維持しながら、段階的に法人経営へ移行していく方法を検討することも一つの選択肢です。
マンション経営を法人化する流れ
マンション経営の法人化は複数のステップを経て行われます。ここでは、その具体的な流れと各段階での注意点を解説します。
Step1.法人の種類を決める
法人化を進める際には、まず法人の種類を決める必要があります。一般的には、株式会社や合同会社などの選択肢があります。株式会社は合同会社に比べて社会的信用が高く、資金調達がしやすい一方で、設立費用が高くなる傾向があります。合同会社は設立費用が比較的安く、柔軟な運営がしやすいため、初めて法人化を行う場合におすすめです。設立後に会社の種類を変更することもできますが、手続きが複雑になるため、慎重に選択しましょう。
Step2.会社の基本事項を決めて定款を作成する
法人化するうえで、会社名や所在地、事業内容などの基本事項を決める必要があります。これらの基本事項をもとに、法人の定款を作成します。定款は会社の基本的なルールを定める重要な書類であり、公証役場で認証を受けたうえで法務局に提出する必要があります。定款の作成には専門的な知識が必要なため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。またこのタイミングで会社印(代表者印)を作成しておくと、後の流れがスムーズに進められるでしょう。
Step3.設立登記をする
定款の認証を受け、資本金の払い込み(代表者の個人口座への入金)を済ませたら、設立登記に進みます。登記申請書や定款、印鑑届出書、資本金の払い込みを証明する書類などの必要書類を準備し、法務局に提出しましょう。登記が完了すると、法人としての活動が正式に認められます。登記手続きには時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を進めることが重要です。
Step4.税務署に法人の開業届を提出する
法人を設立した後は、2カ月以内に税務署に法人の開業届(法人設立届出書)を提出する必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。同時に青色申告の手続きを行うと、税務上のメリットを享受することができます。青色申告とは、一定の要件を満たすことで、欠損金の繰越控除や30万円未満の減価償却資産の一括経費化などの優遇を受けられる制度です。青色申告を行うことで、法人としての税負担を軽減することが可能です。
参考:「少額減価償却資産の特例」(中小企業庁)
以上の手順を踏むことで、マンション経営の法人化が完了します。ただし、各ステップにおいて専門的な知識や判断が必要となるケースも多いため、税理士や司法書士などの専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。また、設立後も適切な会計処理や税務申告が求められるため、継続的な専門家との連携が重要です。
マンション経営の悩みに関するご相談は新日本コンサルティングまで!
マンション経営の法人化は、税金対策や資産管理の観点から多くのメリットをもたらす可能性がありますが、同時に慎重な計画と適切な運営が求められます。法人化に伴う手続きやコストをしっかりと把握し、計画的に進めていきましょう。
また、法人化後の経営においても、税務や法務の専門家のサポートを受けることが有効です。特に、賃貸管理や経営については、信頼できる不動産会社をパートナーにすることが安定経営を実現するうえでは欠かせません。賃貸管理や経営について、必要な時にすぐに相談できる体制を整えることで、安心して経営を続けることができるでしょう
新日本コンサルティングは、マンション経営に関する豊富な経験と専門知識を持ち、物件選びから運営管理、法人化まで、マンション経営に関する総合的なサポートを提供しています。マンション経営に興味のある方は、ぜひ以下から気軽に資料請求やお問い合わせください。