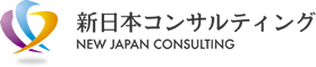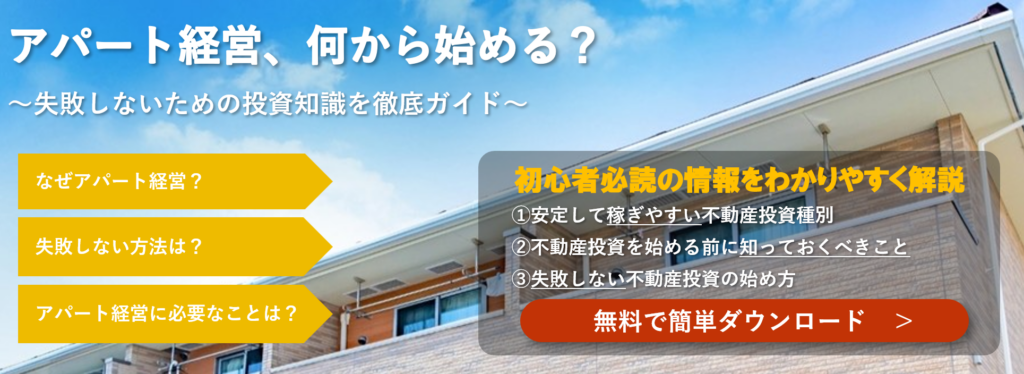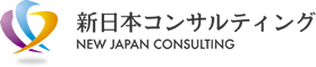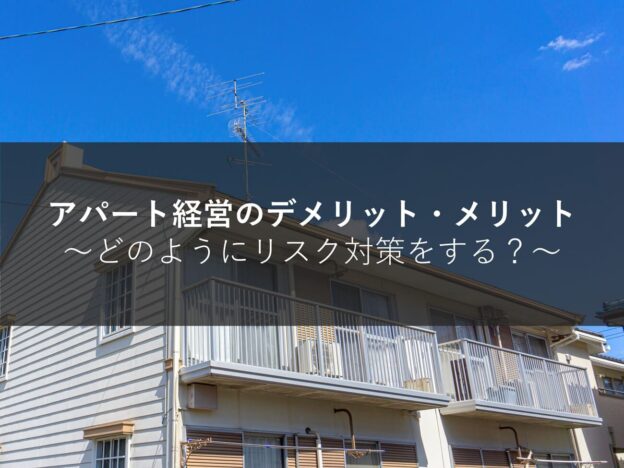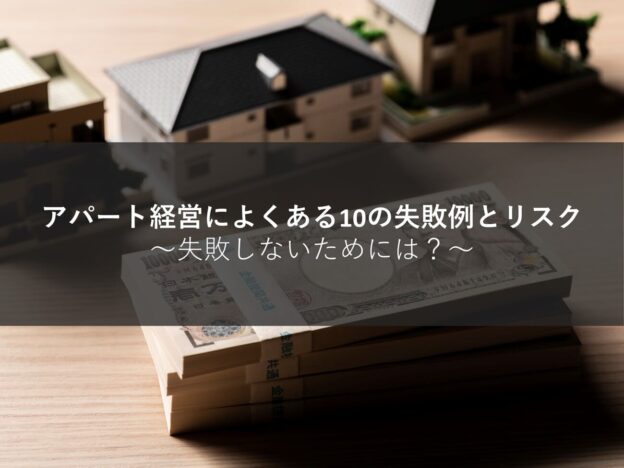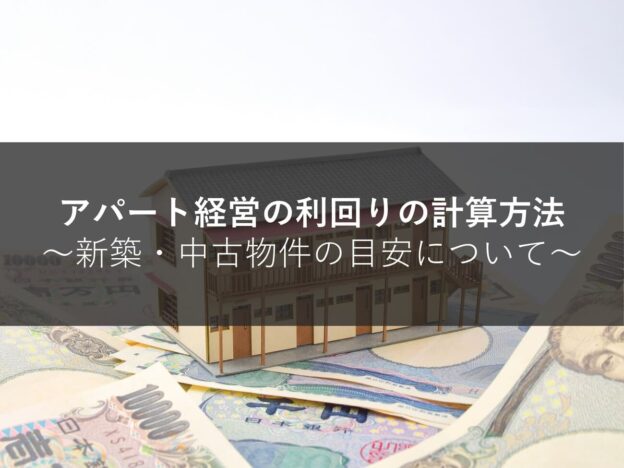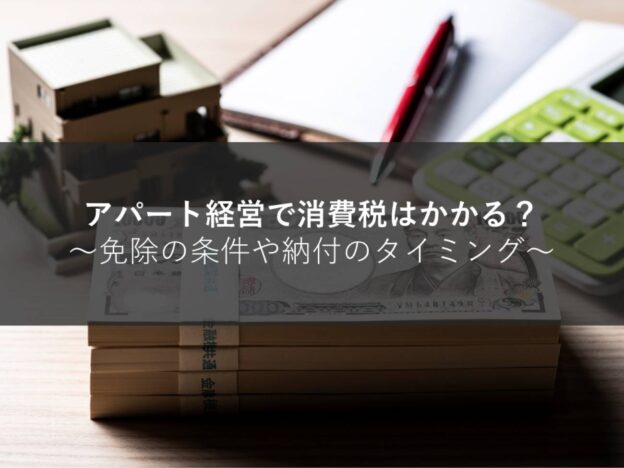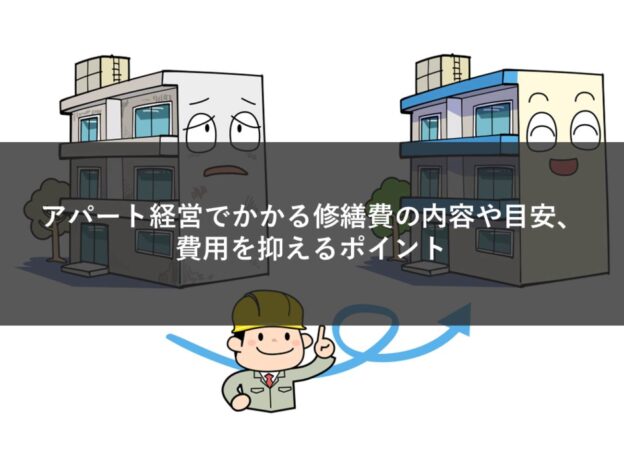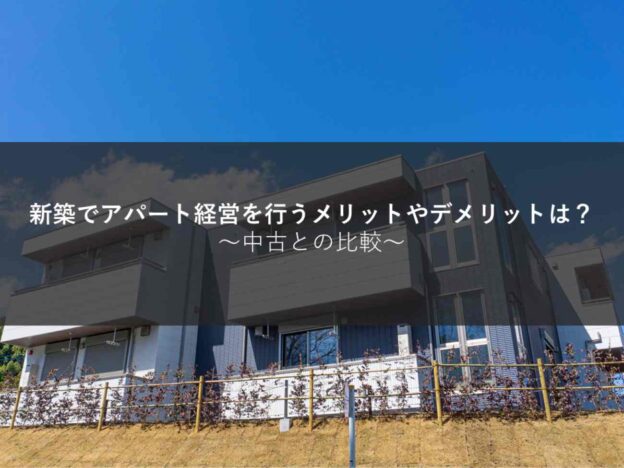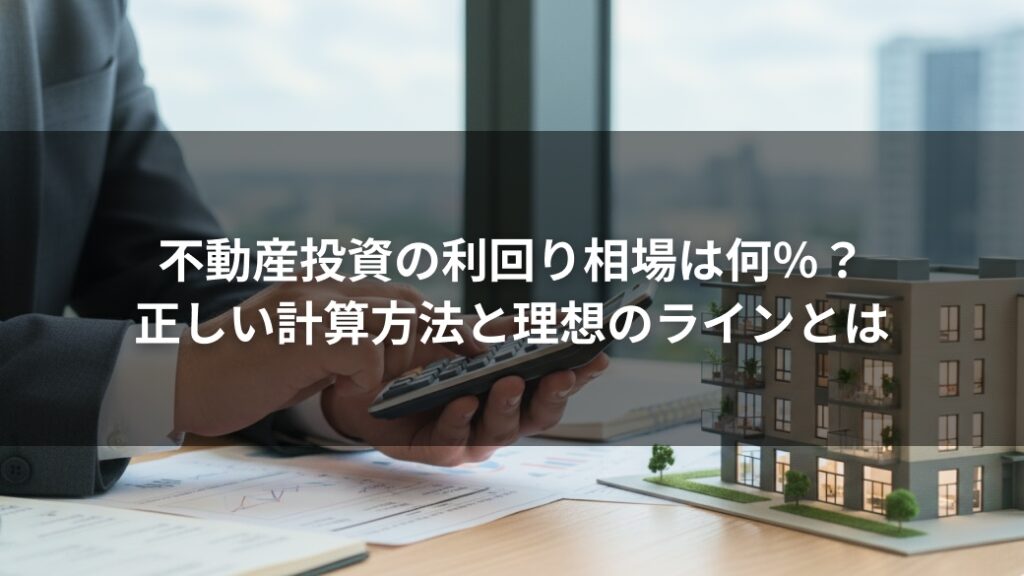
不動産投資を始めるにあたり、多くの人が注目するのが「利回り」です。
利回りは物件の収益性を測るための重要な目安ですが、その計算方法や相場を正しく理解しなければ、投資の成功は遠のきます。
この記事では、不動産投資における利回りの基本的な意味から、3種類の計算方法、物件タイプ別の相場、そして目指すべき理想のラインまでを解説します。
利回りだけでなく、投資判断に必要な他の要素も併せて理解し、安定した資産形成への第一歩としましょう。
目次
不動産投資における「利回り」とは収益性を測るための重要な指標
不動産投資における利回りとは、物件の購入価格に対してどれくらいの収益が見込めるかを示す割合のことです。
この指標は、物件の収益性を客観的に判断するための重要な判断基準となります。
利回りを理解することは、複数の物件を比較検討したり、自身の投資目標に合致しているかを確認したりする上で欠かせません。
不動産投資の基本用語として、その意味と計算方法を初めにしっかりと把握しておくことが、適切な投資判断の基礎を築きます。
【基礎知識】不動産投資で使われる3種類の利回りと計算方法
不動産投資の利回りには、主に「表面利回り」「実質利回り」「想定利回り」の3種類が存在します。
初めにそれぞれの意味と計算式を理解し、物件を比較する際にどの利回りが使われているかを見極めることが重要です。
表面利回りは最も簡易的な式で算出される一方、実質利回りは諸経費を考慮するため、より現実に近い収益性を表します。
それぞれの特徴を解説するので、目的に応じて使い分けられるようにしましょう。
年間家賃収入を物件価格で割る「表面利回り」の計算方法
表面利回り(グロス利回り)は、年間の家賃収入を物件の購入価格で割ることで算出される、最も単純な指標です。
| 表面利回り = 年間家賃収入 ÷ 物件購入価格 × 100 |
この計算方法は非常に簡単で、大まかな収益性をすぐに把握できるため、不動産広告などで一般的に用いられることが多いです。
しかし、この数値には物件の購入時にかかる諸経費や、運営していく上で必要な管理費、税金などのコストが含まれていません。
そのため、あくまで物件を比較検討する際の初期段階の目安として捉え、この割合だけで投資を判断しないように注意が必要です。
購入時の諸経費や運営費を考慮した「実質利回り」の計算方法
実質利回り(ネット利回り)は、年間の家賃収入から運営にかかる諸経費を差し引いた金額を、物件の購入価格に購入時の諸費用を加えた合計額で割って算出します。
| 実質利回り = (年間家賃収入 - 年間諸経費)÷(物件購入価格 + 購入時諸費用)× 100 |
年間諸経費には、管理費や修繕積立金、固定資産税、火災保険料などが含まれ、より現実的なキャッシュフローに近い数値を把握できます。
計算は複雑になりますが、手元に残るお金を正確にシミュレーションするためには、この実質利回りを考慮することが不可欠です。
購入時にかかる不動産取得税なども費用に含めるため、表面利回りよりも低くなります。
満室を想定して算出される「想定利回り」の計算方法
想定利回りは、新築物件や現在空室のある物件で、満室になったと仮定した場合に得られる予想の年間家賃収入をもとに算出される利回りです。
計算方法は表面利回りと同じですが、収入部分が実績ではなく、あくまで満室を想定した期待値である点が異なります。
例えば、全10戸のアパートで2戸が空室でも、10戸すべてが入居しているものとして計算します。
この数値は、将来的な収益の最大値を示すものですが、実際には空室が発生するリスクが加味されていません。
そのため、想定利回りだけを鵜呑みにせず、周辺の賃貸需要や空室率なども踏まえて現実的な収益を予測する必要があります。
【物件タイプ別】不動産投資の利回り平均相場はどのくらい?
不動産投資の利回りは、物件のタイプやエリア、新築か中古か、によって異なります。
物件の表面利回りは「年間家賃収入÷物件購入価格×100」で計算さるため、「年間家賃収入」が高いと利回りも高くなり、「物件購入価格」が低いと利回りは高くなります。
例えば、都心部の物件は価格が高いため利回りが低くなる一方、地方の物件は価格が安いため利回りが高くなる傾向にあります。
また、新築物件と中古物件では、中古物件のほうが価格が低い傾向にあるため、利回りは中古物件のほうが高い傾向にあります。
ここではあくまで目安として、代表的な物件タイプごとの全国平均での利回りを紹介し、それぞれの特徴を解説します。
データ引用:「不動産投資と収益物件の情報サイト健美家(けんびや)」
区分マンションの利回り相場
2025年9月時点の全国平均表面利回りは6.69%ですが、都心部の区分マンションではこれよりも低い3〜4%台になるケースも珍しくありません。
区分マンションの中でも特にワンルームマンションは、都心エリアで多数供給されており、需要の高さから物件価格が高騰しているため、利回りは低い水準で推移する傾向があります。
しかし、利回りが低いからといって一概に投資価値が低いわけではなく、都心部のマンションは資産価値が安定しており、流動性が比較的高いというメリットがあります。
一棟アパートの利回り相場
一棟アパートの利回り相場は、2025年9月時点で全国平均表面利回り8.04%です。
一棟アパートは、建物全体を所有するため、複数の部屋から家賃収入を得ることができ、空室リスクを分散できるというメリットがあります。地方の物件では、需要や供給のバランスから物件価格が都心部よりも手頃な場合が多く、利回りが高く設定されていることがあります。
しかし、投資を検討する際は、物件の賃貸需要や将来的な建物の修繕費用なども考慮に入れることが重要です。
一棟マンションの利回り相場
2025年9月時点で、全国平均の表面利回りは7.51%です。一棟アパートや一棟のマンションは、土地も合わせて所有できるため、区分マンションよりも資産性が高い点が魅力です。
特に地方にある一棟マンションは、物件価格が1億円を超えるような場合でも、さらに高い利回りを期待できることもあります。
複数の部屋から家賃収入を得ることで空室リスクを分散できる点はオーナーにとってメリットですが、高額な投資となるため、相応の自己資金と経営に関する知識が求められます。
不動産投資で目指すべき利回りの理想ラインを解説
不動産投資において、目指すべき利回りに絶対的な基準はありません。
物件の種別、立地、築年数、そして個々の投資戦略によって理想のラインは変動します。
重要なのは、利回りの相場を把握した上で、自身が許容できるリスクの範囲内で、最低限どれくらいの収益が必要かを設定することです。
ローン金利や諸経費を考慮し、現実的な目標を立てることが成功への鍵となります。
目標にしたい理想的な利回りの目安
目標とすべき理想の利回りは、物件の種類やエリアによって大きく異なりますが、一つの目安として実質利回りで4〜5%以上を確保することが望ましいとされます。
地方の築古物件など、リスクが高い投資では10%や12%を超える高利回りを狙うケースもありますが、それに伴い空室や修繕のリスクも増大します。
中には20パーセントや30パーセントといった非常に高い利回りをうたう物件も存在しますが、相応の理由があることがほとんどです。
自身の投資スタイルやリスク許容度に応じて、どの程度の利益を確保したいのかを明確にし、現実的な目標を設定する必要があります。
利回りだけで判断は危険!
高い利回りの物件は一見魅力的に映りますが、その数値だけで投資を判断するのは非常に危険です。
特に注意すべきなのは、不動産投資ローンを利用する場合の金利との関係です。
物件の利回りから借入金の金利を差し引いた「イールドギャップ」が、実質的な利益の源泉となります。
たとえ利回りが高くても、ローンの金利が高ければ手元に残るキャッシュフローは少なくなります。
返済の負担が大きくなりすぎると、空室が発生した際に経営が立ち行かなくなる可能性もあり、投資の失敗につながりかねません。
高利回り物件に潜む注意点!購入前に確認すべきリスク
利回りが相場よりも極端に高い物件には、何らかの理由が隠されていることが少なくありません。
高利回りというメリットの裏に潜むリスクを事前に確認し、慎重に判断することが重要です。
価格が安い理由を深く掘り下げ、空室や修繕、法的な問題など、将来の収益を圧迫する要因がないか、購入前にしっかりとチェックするべき注意点があります。
築年数が古く、多額の修繕費が発生する可能性
高利回り物件の多くは、築年数が経過した中古物件です。
物件の取得価格が安いため利回りは高くなりますが、その分、建物の老朽化が進んでいる可能性が高いです。
購入当初は問題がなくても、数年後に給排水管の交換や屋上の防水工事といった大規模修繕が必要になることがあります。
これらの修繕費は高額になるケースが多く、当初の利回りシミュレーションを大幅に狂わせる要因となります。
計画的なメンテナンスがなされてきたか、将来的にどのような修繕コストが発生する可能性があるか、事前に確認することが重要です。
駅から遠いなど立地条件が悪く、空室が埋まりにくい
物件価格が安い理由として、立地条件の悪さが挙げられます。
最寄り駅から徒歩圏外であったり、周辺にスーパーやコンビニなどの生活利便施設が乏しかったりするエリアは、賃貸需要が低くなる傾向があります。
このような物件は入居者が見つかりにくく、空室期間が長引くリスクを抱えています。
また、入居者を確保するために賃料を下げざるを得ず、結果的に想定していた利回りを下回ることもあります。
購入を検討する際は、現地に足を運ぶことが望ましく、周辺環境や実際の入居者の稼働状況を確認し、安定した賃貸経営が見込めるかどうかの対策を考える必要があります。
事故物件などの心理的瑕疵が隠れているケース
相場より著しく利回りが高い場合、その物件が過去に事件や事故があった「心理的瑕疵物件」である可能性も考えられます。
不動産会社には買主への告知義務がありますが、その説明が不十分なケースや、巧妙に隠されているトラブルも存在します。
心理的瑕疵は入居者が定着しにくい大きな要因となり、高額な家賃下落につながるリスクを伴います。
安さの理由に少しでも疑問を感じたら、納得がいくまで事前調査を行い、不動産会社に詳細な説明を求めることが重要です。
安易な判断は将来の大きなトラブルを招きかねません。
利回りが低くても魅力的な物件に共通する4つの特徴
利回りの数値が低いからといって、その物件が投資対象として魅力がないわけではありません。
むしろ、利回りが低い物件には、長期的に安定した資産運用を可能にするメリットが隠れていることがあります。
資産価値が下がりにくく、安定した需要が見込めるなど、利回りの高さだけでは測れない「良い物件」の選び方には4つの特徴があります。
これらのポイントを理解することで、より賢明な投資判断が可能になります。
人気エリアにあり資産価値が下がりにくい
都心部や再開発が進む人気エリアに位置する物件は、購入価格が高いため利回りは低くなる傾向にあります。
しかし、これらのエリアは交通の便や生活環境が良く、常に高い賃貸需要が見込めるため、資産価値が下がりにくいという大きなメリットがあります。
管理が行き届いており建物の状態が良い
建物の管理状態は、将来の収益性を大きく左右する要素です。
定期的な清掃やメンテナンスが行き届き、長期修繕計画が適切に立てられている物件は、築年数が経過していても良好な状態を保てます。
これにより、突発的な高額修繕費の発生リスクを低減させ、安定した運用が可能になります。
物件の室内だけでなく、共用部分の状態や管理会社の委託状況などを確認することで、その物件が大切に維持されてきたかどうかを判断できます。
管理状態の良い物件は入居者にとっても魅力的であり、安心して長く住んでもらえることにつながります。
安定した賃貸需要で入居者が途切れない
利回りが低くても、常に満室に近い稼働率を維持できる物件は、結果的に安定した収益を生み出します。
大学や大規模な企業の近く、あるいは交通の結節点となる駅の周辺など、賃貸マーケットにおいて確固たる需要が存在するエリアの物件は、入居者が途切れにくいという強みがあります。
不動産賃貸経営の最大のリスクは空室であるため、このリスクを最小限に抑えられることは大きな魅力です。
周辺の人口動態や競合物件の状況を調査し、将来にわたって安定した需要を確保できるか見極めることが重要です。
売却しやすく出口戦略が立てやすい
不動産投資は、家賃収入(インカムゲイン)だけでなく、最終的な売却(キャピタルゲイン)までを見据えた出口戦略が重要です。
人気エリアにある物件や、管理状態が良好な物件は、不動産市場において常に需要があるため、売りたいタイミングで買い手を見つけやすいというメリットがあります。
流動性が高い物件は、将来の経済状況の変化やライフプランの変更にも柔軟に対応できます。
購入時点から、どのような条件なら売却できるかをシミュレーションし、出口戦略が立てやすい物件を選ぶことは、賢明な投資判断の基本です。
不動産投資で成功するために見るべき他の要素
不動産投資の成功は、利回りという単一の指標だけで決まるものではありません。
そのため、物件を評価する際には、利回りと密接な関係にある他の要素も重視する必要があります。
入居率や資金計画、そして最終的な出口戦略といった複数のポイントを総合的に検討することで、リスクを管理し、長期的に安定した収益を目指すことが可能になります。
実際の収益に影響する入居率の高さ
利回りの計算は満室を想定していることが多いですが、実際の収益は入居率によって大きく変動します。
代表的な指標である利回りが高くても、空室が多ければ計画通りのキャッシュフローは得られません。
物件の立地や周辺環境、建物の管理状態などを調査し、将来にわたって高い入居率を維持できるかどうかの見極めが不可欠です。
周辺物件の空室率や家賃相場を参考に、現実的な入居率を想定した上で収支シミュレーションを行うことが、投資の精度を高める上で重要です。
長期的な安定運用を支える資金計画
不動産投資では、自己資金とローンのバランスを考えた無理のない資金計画が大切です。
少ない自己資金で大きな物件を購入できるレバレッジ効果は魅力ですが、過度な借入は金利上昇時や空室発生時のリスクを高める可能性があります。
空室期間中のローン返済や、急な修繕費の発生にも対応できるよう、手元にはある程度の余裕資金を残しておくべきです。
物件価格だけでなく、購入時の諸費用や将来の運営コストまで含めた長期的な視点で、安定した運用を支える資金計画を立てることが求められます。
将来の売却まで見据えた出口戦略
不動産投資は、物件を所有している間の家賃収入だけでなく、最終的に売却して投資資金を回収するまでが一つのサイクルです。
購入する段階から、何年後にいくらで売却する予定なのか、具体的な出口戦略を立てておくことが重要です。
例えば、10年後に売却する場合、その時点での建物の価値や周辺の市場環境がどう変化しているかを予測する必要があります。
流動性が低く、売却したいときに売れない物件は、最終的な投資回収の期間が長引くリスクを抱えています。
出口を見据えて物件を選ぶ視点が、投資全体の成否を左右します。
まとめ
この記事では、不動産投資における利回りについて、その計算方法から相場、リスクまで解説しました。
利回りは重要な指標ですが、1つの数値だけで物件の価値を判断することはできません。表面的な数値に惑わされず、実質利回りや入居率、維持管理費、出口戦略といった多角的な視点から物件を評価することが、安定した不動産投資の第一歩となります。
新日本コンサルティングでは、物件選びから収支シミュレーション、購入後の賃貸管理まで、不動産投資を総合的にサポートしています。利回りやキャッシュフローを最大化するための具体的なアドバイスも行っていますので、不動産投資にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。