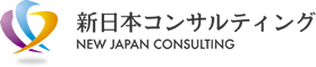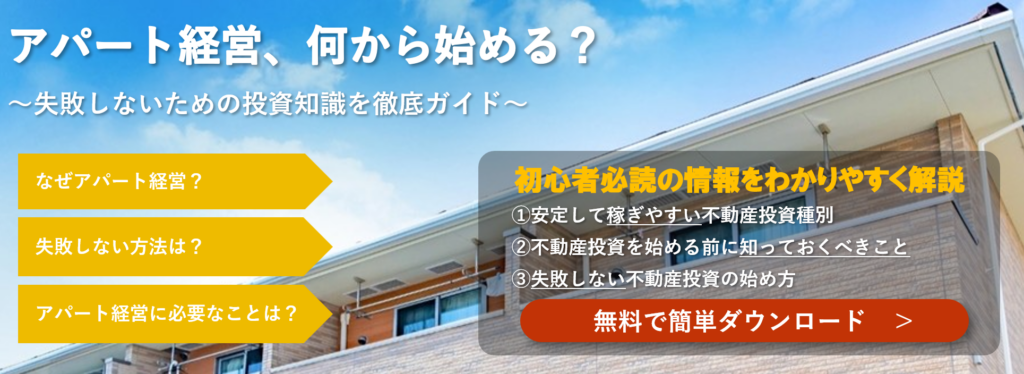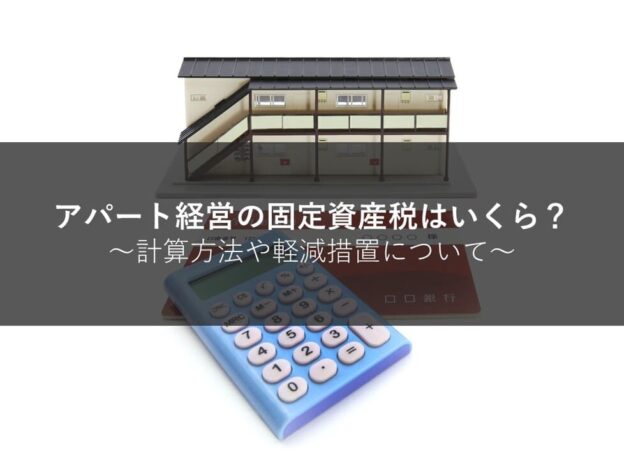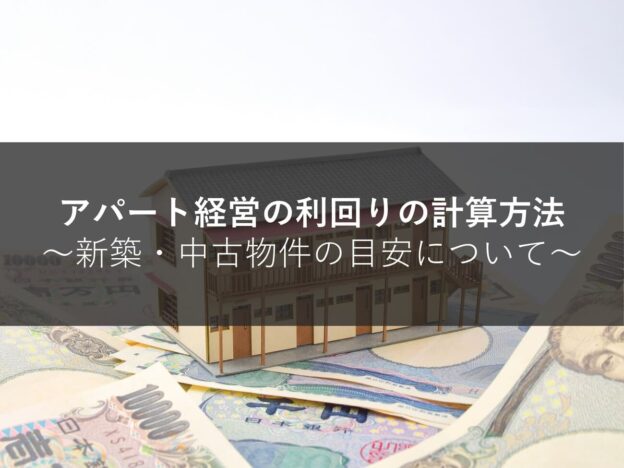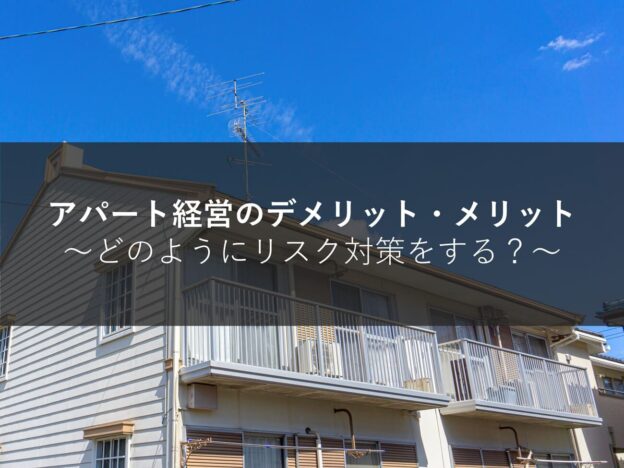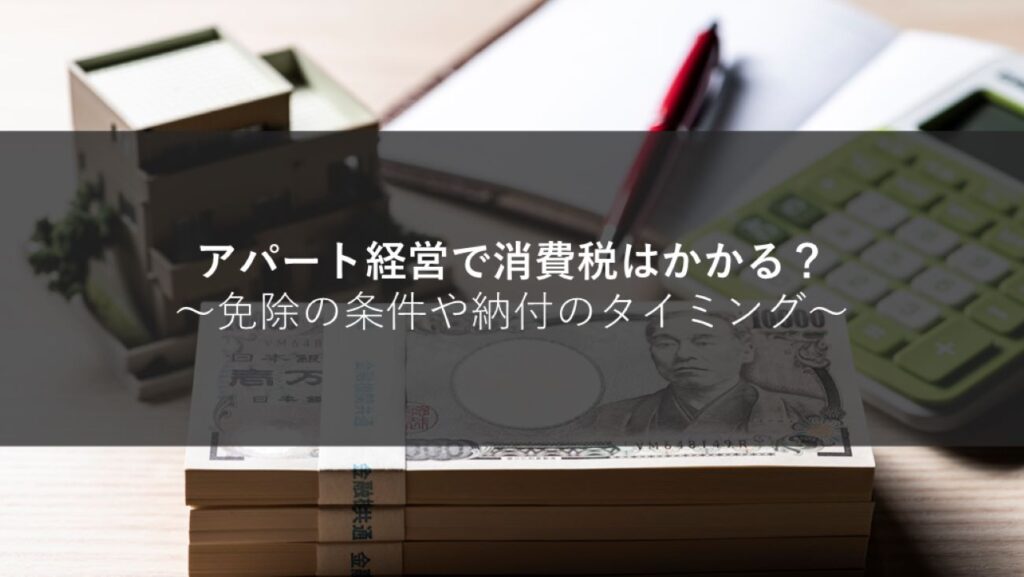
目次
アパート経営を始める際に消費税はかかる?

アパート経営を始める際には、さまざまな初期費用がかかります。この初期費用のうち、消費税が課税されるものとされないものがありますので、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
アパート経営の初期費用で消費税の対象になるもの(課税取引)
アパート経営を始める際に発生する初期費用の中で、消費税がかかる具体的な項目について詳しく解説します。
アパートの建築費用
アパートの建築費用には消費税がかかります。これは、建築業者が提供する建築サービスに対する対価として消費税が課されるためです。具体的には、以下のような費用が含まれます。
| 設計費用 | 建築士や設計事務所に支払う設計料 |
| 工事費用 | 建設会社や工務店に支払う建築工事の費用 |
| 資材費用 | 建築に使用する材料の購入費用 |
これらの費用には一律で10%の消費税がかかります。
建物の売買代金
法人が売主の場合、建物の売買代金には消費税がかかります。これは法人が行う事業活動としての売買に対して消費税が課されるためです。
| 新築物件 | 法人が新築したアパートを販売する場合、その売買代金には消費税が適用されます |
| 中古物件 | 法人が所有する中古アパートを販売する場合も同様に消費税がかかります |
土地や建物の登記関連費用
登記関連の手数料には消費税がかかります。これには司法書士や土地家屋調査士が提供するサービスに対する対価として消費税が課されるためです。
| 司法書士手数料 | 司法書士が行う所有権移転登記や抵当権設定登記などの業務に対する手数料 |
| 土地家屋調査士手数料 | 土地や建物の境界確定や分筆などの業務に対する手数料 |
不動産会社等への仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。不動産取引におけるサービス提供に対する対価として消費税が課されるためです。
| 売買仲介手数料 | アパートの売買に際して不動産会社に支払う手数料 |
| 賃貸仲介手数料 | アパートの賃貸契約を結ぶ際に不動産会社に支払う手数料 |
諸手続きで発生する手数料
金融機関に支払うローン事務手数料などの手数料には消費税がかかります。これらは金融機関が提供するサービスに対する対価として消費税が課されるためです。
| ローン事務手数料 | 銀行や金融機関に支払う住宅ローンの事務手数料 |
| 保証料 | ローン保証会社に支払う保証料にも消費税がかかります |
これらの費用に対する消費税の正確な理解は、アパート経営の初期コストを適切に把握し、資金計画を立てる際に役立ちます。
アパート経営の初期費用で消費税の対象にならないもの(非課税取引)
アパート経営を始める際に発生する初期費用の中で、消費税の対象とならない非課税取引について詳しく解説します。
土地の売買代金
土地の売買代金に消費税はかかりません。これは、土地の売買が非課税取引に該当するためです。
| 土地の購入 | アパート用地として購入する土地の売買代金は非課税です。これは、土地そのものの価値に対して消費税が適用されないためです。 |
建物の売買代金
非課税業者が売主の場合、建物の売買代金には消費税がかかりません。これは、特定の非課税業者による売買が消費税法上非課税となるためです。
| 非課税業者が売主の場合 | 個人や特定の小規模事業者が売主の場合、建物の売買代金は非課税となることがあります。具体的には、年間売上が一定金額未満の事業者や非課税事業者が該当します。 |
火災や地震などに備えるための保険料
アパートの火災や地震などのリスクに備えるための保険料に消費税はかかりません。これは、保険料が消費税法上非課税とされるためです。
| 火災保険料 | アパートの建物や設備を火災から守るための保険料 |
| 地震保険料 | 地震による損害に備えるための保険料 |
住宅ローンの保証料
住宅ローンの保証料も消費税の対象外です。これは、金融商品としての保証サービスが非課税取引に該当するためです。
| ローン保証料 | 住宅ローンを借り入れる際に必要な保証会社に支払う保証料。保証料は金融商品としての性質があり、消費税法上非課税です |
これらの非課税取引に該当する初期費用について正確に理解することは、アパート経営における資金計画を立てる際に重要です。これにより、不要な消費税負担を避けられます。
関連記事:アパート経営を始めるときに必要な初期費用とは?内訳や金額の目安をご紹介
アパート経営の運用時にかかる消費税は?

アパート経営の運用には課税対象となる取引と、非課税対象となる取引の2つがあります。
それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
アパート経営の運用時に消費税の対象になるもの(課税取引)
アパート経営の運用時には、いくつかの費用や収入が消費税の対象となります。具体的な項目について詳しく解説します。
居住目的以外の家賃収入
事務所や店舗など、居住以外の目的でアパートの一部を貸し出す場合、その家賃収入には消費税がかかります。
事業用物件の礼金
事業用物件に対する礼金には消費税がかかります。これは、事業活動に関連する取引として消費税が適用されるためです。
家賃と別に請求している水道光熱費
居住者に対して家賃とは別に請求する水道光熱費には消費税がかかります。
管理会社へ支払う管理委託料や修繕費
アパートの管理を委託する管理会社への支払いや修繕費には消費税がかかります。
備品の購入費
アパートの運営に必要な備品の購入費には消費税がかかります。
共用部分の水道光熱費
アパートの共用部分にかかる水道光熱費には消費税がかかります。
居住者の希望によって付帯した設備の利用料
居住者の希望に応じて提供する追加設備の利用料には消費税がかかります。
賃貸借期間が1カ月未満の契約で得た家賃収入
短期賃貸契約(1カ月未満)の家賃収入には消費税がかかります。
これらの項目について正確に把握しておくことで、アパート経営における収入や支出の消費税計算が正確に行えるようになります。
アパート経営の運用時に消費税の対象にならないもの(非課税取引)
一方で、アパート経営の運用時には、いくつかの費用や収入が消費税の対象とならない非課税取引があります。具体的な項目について詳しく解説します。
居住目的の家賃収入
居住目的で貸し出すアパートの家賃収入に消費税はかかりません。これは、居住用賃貸借契約に基づく家賃収入が非課税取引に該当するためです。
駐車場
駐車場代が非課税となる要件は、駐車場が居住者専用であり、住宅の一部として提供される場合です。
共益費
居住者から徴収する共益費に消費税はかかりません。共益費は居住者が共同で使用する施設や設備の維持管理費用として徴収されるものであり、家賃と同様に非課税となります。
敷金
敷金は退去時に返還される場合、消費税の対象とはなりません。これは、敷金が預かり金としての性質を持ち、消費の対価としての性質を持たないためです。
契約の更新料
居住用物件の賃貸借契約の更新時に支払われる更新料に消費税はかかりません。これは、更新料が契約延長のための費用として非課税取引に該当するためです。
居住用物件の礼金
居住用物件の礼金は消費税の対象外です。これは、居住用賃貸借契約に関連する費用として非課税取引に該当するためです。
家賃に含まれた水道光熱費
家賃に含まれている水道光熱費も非課税です。これは、家賃の一部として扱われるためです。
ローン返済の利子
アパート経営のためのローン返済における利子に消費税はかかりません。これは、金融取引における利子が非課税取引に該当するためです。
銀行や金融機関へのローン返済の利子。
これらの非課税取引に該当する項目について正確に理解することは、アパート経営における経費の管理や税務処理を正確に行うために重要です。
家賃収入に消費税が課税されない理由
家賃収入に消費税が課税されない主な理由は、居住用の家賃は非課税取引とされているためです。この非課税の適用条件として、「契約書に居住用である旨が明記されており、賃貸期間が1ヶ月以上であること」が求められます。
賃貸物件の家賃収入は、消費税の導入当初は課税対象の取引とされていた
1989年に消費税が導入された当初、賃貸物件の家賃収入は課税対象の取引とされていました。しかし、短期間で税制が改正されることとなります。
平成3年10月に税制が改正され、居住用の家賃収入は非課税となった
1991年(平成3年)10月に税制が改正され、居住用の家賃収入が非課税取引に変更されました。この変更により、居住用賃貸物件の家賃に対して消費税を課すことがなくなりました。
消費税を課税しない例外的な取引に当てはまったため
居住用の家賃収入が非課税とされた理由は、消費税を課税しない例外的な取引に当てはまるためです。以下のような社会政策的配慮や課税の対象として馴染まない取引が対象とされます。
社会政策的配慮が必要な取引
居住用の賃貸物件は、多くの人々が生活するために必要不可欠なものであり、これに消費税を課すことは社会的に適切ではないと判断されました。特に低所得者層への負担を軽減するため、居住用家賃を非課税とすることで生活の安定を図る意図がありました。
課税の対象として馴染まない取引
居住用家賃は、長期間にわたり定期的に支払われるものであり、消費税を適用することで計算や徴収が複雑化するため、課税の対象として馴染まないとされました。また、居住用賃貸契約は基本的に生活のためのものであり、商業活動とは異なる性質を持つため、消費税の課税対象から除外されました。
注意点:店舗や事務所などの事業用家賃収入については課税対象
一方で、店舗や事務所などの事業用家賃収入については消費税が課税されるため注意が必要です。事業用賃貸物件の家賃収入は、消費税法上、課税取引として取り扱われます。
住宅用家賃収入が1,000万円を超える場合
なお、住宅用家賃収入が1,000万円を超える場合、「課税売上額」として取り扱われる可能性がありますので、個人事業主の方は特に注意が必要です。これは、消費税の免税事業者としての基準に影響を及ぼすためです。
これらの理由により、居住用の家賃収入は非課税となり、賃貸物件の運営者や入居者にとって重要な税制上のメリットとなっています。この非課税措置は、今後も居住用物件の提供と利用を支える重要な要素として機能し続けるでしょう。
アパート経営における消費税の免除や還付の条件
アパート経営で消費税が免除になるケース
アパート経営において、特定の条件を満たす場合、消費税が免除されるケースがあります。以下に、免除の対象となる主なケースと、例外として免除の対象にならない場合について説明します。
前々年の課税売上高が1,000万円以下
アパート経営者の前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、その年の消費税が免除されます。これは、消費税法に基づく免税事業者の基準に該当するためです。
前々期の課税売上高が1,000万円以下
法人の場合、前々期(事業年度の2期前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、同様に消費税が免除されます。
課税事業者選択届出書を提出していない
課税事業者選択届出書を税務署に提出していない場合、消費税が免除されます。この届出書を提出することで、課税事業者としての義務を負うことになりますが、提出しなければ免税事業者として扱われます。
事業開始した年やその翌年
新たに事業を開始した年やその翌年についても、消費税が免除されるケースがあります。これは、事業開始初期の負担を軽減するための措置として設けられています。
例外として免除の対象にならないケース
免税の対象となる条件を満たさない場合、消費税が課されることになります。以下のようなケースが該当します。
これらのケースを理解し、適切に対応することで、アパート経営における消費税の負担を最小限に抑えられます
アパート経営で消費税の還付金を受け取れるケース
アパート経営において消費税の還付金を受け取れるケースは多くありません。しかし、特定の条件を満たす場合には還付を受けることが可能です。ここでは、消費税が還付される条件と具体例について説明します。
消費税が還付される条件
消費税が還付されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
アパート経営で消費税が還付されるケースの具体例
アパート経営において、消費税の還付を受けられる具体的なケースとしては、以下のような状況があります。
新築アパートの建設や大規模リフォーム
アパートの建設や大規模なリフォームを行った場合、その費用に対する消費税が多額となります。この場合、事業用賃貸による課税売上がある場合には、その差額分の消費税が還付される可能性があります。
事務所や店舗の併設
居住用アパートに事務所や店舗を併設し、それらの賃貸収入がある場合。これらの賃貸収入は課税売上として扱われるため、仕入れや経費に対する消費税との差額が還付されることがあります。
アパートの共用部分のリフォーム費用に対する消費税が店舗賃貸収入に対する消費税よりも多い場合、その差額が還付されます。
高額な設備投資
アパートの運営において、エレベーターやセキュリティシステムなどの高額な設備投資を行った場合。これに対する消費税が大きく、事業用賃貸の課税売上がある場合には、その差額が還付されることがあります。
事業用の課税売上に対する消費税が100万円であれば、差額の100万円が還付されます。
これらのケースに該当する場合、消費税の還付を受けることでアパート経営の資金繰りを改善できます。還付を受けるためには、適切な手続きを行うことが重要ですので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
アパート経営で納める消費税の計算方法
アパート経営において消費税の計算は非常に重要な要素です。消費税の計算方法には、「簡易課税方式」と「原則課税方式」の2つの方法があります。これらは、経営者がどちらを選択するかによって、納める消費税の金額が大きく変わる可能性があります。
簡易課税方式とは
簡易課税方式とは、中小企業や小規模事業者向けに設けられた消費税の計算方法です。この方式では、実際の仕入れや経費の額を基に消費税の控除を行う代わりに、一定の割合(みなし仕入れ率)を使用して簡便に計算します。これにより、経理の手間を大幅に軽減できます。
適応する条件
簡易課税方式を適用するためには、いくつかの条件があります。
適用するメリット
簡易課税方式には、以下のようなメリットがあります。
納税額の計算方法
簡易課税方式における納税額の計算方法は以下の通りです。
みなし仕入れ率は、業種ごとに定められており、売上に対する仕入れや経費の割合を示しています。
主な業種のみなし仕入れ率は以下の通りです。
第1種事業(卸売業):90%
第2種事業(小売業):80%
第3種事業(製造業など):70%
第4種事業(その他の事業):60%
第5種事業(サービス業など):50%
第6種事業(不動産業など):40%
例えば、課税売上高が3,000万円で、受け取った消費税額が300万円、事業が第5種事業(サービス業)である場合、みなし仕入れ率は50%です。この場合の納税額は以下のように計算されます。
受け取った消費税額:300万円
みなし仕入れ率を用いた控除額:300万円 × 50% = 150万円
納税額:300万円 - 150万円 = 150万円
このように、簡易課税方式を適用することで、納税額の計算が簡便に行えるため、中小企業や小規模事業者にとって非常に有益な制度です。
原則課税方式とは
原則課税方式とは、消費税の計算方法の一つで、主に課税売上高が5,000万円を超える事業者に適用される方式です。この方式では、実際に受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引いて消費税を計算し、より正確に消費税の負担額を反映するため、大規模な事業者向けに設けられています。
原則課税方式の計算式
原則課税方式における消費税の納税額は、以下の計算式で求められます。
受け取った消費税額:売上に対して受け取った消費税額を指します。これは、商品やサービスを提供した際に顧客から受け取る消費税です。
支払った消費税額:仕入れや経費に対して支払った消費税額を指します。これは、事業運営に必要な物品やサービスを購入した際に支払う消費税です。
例えば、ある事業者の課税売上高が6,000万円で、受け取った消費税額が600万円、支払った消費税額が400万円の場合、納税額は以下のように計算されます。
受け取った消費税額:600万円
支払った消費税額:400万円
納税額:600万円 - 400万円 = 200万円
簡易課税方式との違い
原則課税方式は、実際の仕入れや経費に対する消費税額を基に計算されるため、より正確な消費税負担額が求められます。一方、簡易課税方式では、みなし仕入れ率を用いて簡便に計算します。
簡易課税方式は、課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。
簡易課税方式:受け取った消費税額 -(受け取った消費税額 × みなし仕入れ率)
【参考】 「消費税のしくみ」 (国税庁)
これらの点を理解し、適切な消費税の計算方法を選択することで、事業の税務管理がより効率的になります。
アパート経営者が消費税を納めるタイミング
アパート経営に携わっている方にとって、消費税の納付タイミングは重要な検討事項です。適切な納税タイミングを把握することで、キャッシュフローの調整や節税対策が行いやすくなります。以下では、個人事業主の場合と法人の場合について詳しく説明します。
個人事業主の場合
アパート経営をしている個人事業主は、一年間の課税売上高が1,000万円を超える場合、次の年度から消費税の納税義務が発生します。消費税の納付は、年間の売上に基づき計算されますが、その納付タイミングは確定申告と連動しています。
消費税の納付タイミング
具体的には、毎年3月15日までに翌年度の確定申告と併せて消費税の申告書を提出しなければなりません。また、消費税の納付期限は対象年度の翌年の3月末までです。この期間内に、確定申告書を作成し、所轄税務署へ申告を行う必要があります。
課税業者となる条件
課税業者となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
事業用家賃や賃貸期間1カ月未満の住宅用家賃が1,000万円を超えること
事業用の賃貸収入や短期賃貸収入が年間で1,000万円を超える場合、次年度から消費税の納税義務が発生します。
- 年間売上の確認:課税売上高が1,000万円を超えるか確認。
- 確定申告書の作成:翌年度の3月15日までに確定申告書を作成し、消費税申告書も併せて作成。
- 所轄税務署へ申告:所轄税務署に確定申告書と消費税申告書を提出。
- 消費税の納付:対象年度の翌年の3月末までに消費税を納付。
課税売上高の範囲
居住用家賃は非課税ですが、事業用賃貸や1カ月未満の短期賃貸の収入は課税売上に含まれます。
納税義務の開始
課税売上高が1,000万円を超えると、翌年度から課税業者としての義務が生じます。
このプロセスを適切に理解し、期限を守って申告と納付を行うことで、アパート経営における税務管理を円滑に進められます。
法人の場合
法人がアパート経営を行っている場合も、消費税の納付タイミングは非常に重要です。法人の場合、年間の課税売上高が1,000万円を超えると、次年度から課税業者として消費税を納める必要があります。個人事業主と同様に、消費税納付のタイミングは決算期に合わせて行われます。
消費税の納付タイミング
法人の場合、消費税の納付は決算期末から2カ月以内に行わなければなりません。具体的には、課税期間終了日の翌日から2カ月以内に、消費税の申告・納付を行う必要があります。この期間内に確定申告書を作成し、所轄税務署へ申告を行います。
課税業者となる条件
法人が課税業者となるためには、年間の課税売上高が1,000万円を超えることが条件です。これにより、翌年度から消費税の納税義務が発生します。
消費税負担軽減策
法人は消費税負担を軽減するために、以下の対策を検討できます。
簡易課税制度の選択
法人が年間の課税売上高が5,000万円以下である場合、簡易課税制度を選択することで、消費税の計算を簡略化し、負担を軽減できます。この場合、所定の手続きを経て「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
適用税率の見直し
消費税率の見直しや適用税率の変更を検討することで、納付金額の適正化を図れます。
納付の流れ
- 年間売上の確認:課税売上高が1,000万円を超えるか確認。
- 決算期末の確認:法人の決算期末を把握し、その終了日から2カ月以内に消費税の申告・納付を行う。
- 確定申告書の作成:決算期末から2カ月以内に確定申告書と消費税申告書を作成。
- 所轄税務署へ申告:所轄税務署に確定申告書と消費税申告書を提出。
- 消費税の納付:課税期間終了日の翌日から2カ月以内に消費税を納付。
課税売上高の範囲
居住用家賃は非課税ですが、事業用賃貸や1カ月未満の短期賃貸の収入は課税売上に含まれます。
納税義務の開始
課税売上高が1,000万円を超えると、翌年度から課税業者としての義務が生じます。